12/19 「魂炸裂♥ハピエン・メリバ創作BLコンテスト」結果発表!
BLニュースは標準ブラウザ非対応となりました。Google Chromeなど別のブラウザからご覧ください。
2025/11/07 16:00
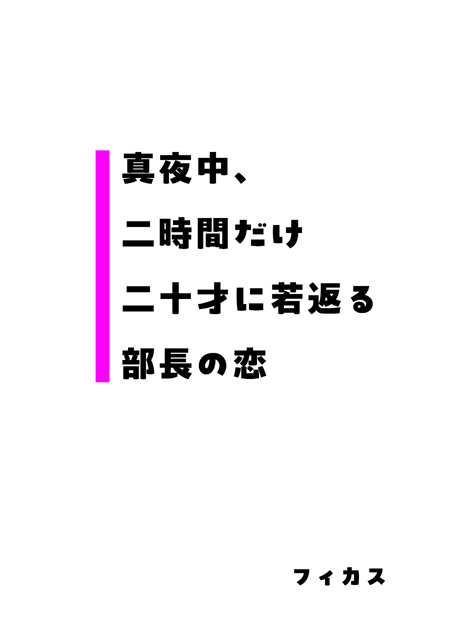
あらすじ
五十四才の山野部長は、夜中のトイレで自分が二十才に若がっていることに気が付く。検証を重ねたところ、夜中二時から四時の間だけ、若がっていることが確定する。
思考回路も若返った山野部長は、恋心を抱く部下の青木(二十八才)と、若返った姿での接触を試み、無事成功。セックスすることができた。
実は青木はおじさん好きで、彼もひそかに山野部長に恋心を抱いていたのだ。
山野部長、若返った山野部長(リョウ)、そして青木の危うくてイヤらしい関係が始まった。
※こちらの作品は性描写がございます※
■第一話【部長】真夜中に若返った性欲
いつからこんな事象が起きていたのかは、分からない。最近なのか、ずっと前からなのか。
はじめて気がついたのは、真夜中のトイレだった。
その日は天気がよく気温も急上昇し、加速するように桜が満開になった。会社の若い子たちから「山野部長も花見がてら、一緒に飲みに行きましょうよ」と誘われ、さりげなく参加メンバーを確認する。
「では一杯だけ」
仕事を切り上げ、社屋すぐそばの焼き鳥り屋に足を運んだ。若者が私に求めているのは、支払いだと重々承知している。ビールを一杯だけ飲み「お先に失礼するよ」と多めの金額を置いて、店を後にした。
格好つけて店を出たものの飲み足りなく、自宅マンションの最寄り駅前でまた居酒屋に入った。何杯か飲んで気持ち良く酔い、少し遠回りだと思いながらも、ライトアップされた桜並木を通って帰る。
満開の桜を見上げていい気分だったのは、歩き始めて五分程度だ。当然といえば当然の尿意が膀胱を襲い、残りの五分はかなり早足でマンションへと急ぐ。
無事にトイレに間に合ったものの、皆の憧れである渋くダンディな部長の仮面は、マンションに辿り着く前に剥がれ落ちてしまった。
必死の形相でトイレを目指す姿は、さぞ情けなかっただろう。
少し落ち込んだ私は、眠い目をこすりながらシャワーを浴び、とっととベッドに入った。
しかし、吞みすぎたビールのせいで、いつもに増して夜中に何度も尿意を感じ、目を覚ます羽目になる。
ゴムが伸びかかったトランクスに手をかけジョボジョボと用を足している時、陰毛に混じりはじめた白髪が、見当たらなかった。
「あれ?」
そう思ったけれど、眼鏡は寝室に置いてきた。どうせ、目が霞んでいるのだろうと何度も瞬きをする。
更に手に持っている陰茎も、いつもよりずっと若々しく艶があるように見えた。
再び「あれ?」と思うも、おかしな夢だと鼻で笑い、ひとりぼっちの寝室へ戻り掛布団をかぶった。
朝起きて、一応眼鏡をかけトイレで確かめれば、年相応の股間がそこにはあった。
この違和感はこの晩だけでは、終わらなかった。
桜も散り始めた頃、真夜中のトイレ後にわざわざ眼鏡をかけ洗面所に行き、鏡の前でトランクスを下ろす。
やっぱり、若返っている……。
そこには遥か昔、若かりし頃の股間が映っていた。上手く状況が飲み込めず、明るい照明の下、しばらく自分の陰茎を見つめてしまう。
ふと我に返り鏡の中をよくよく覗けば、中年らしく弛んきた腹が凹んでいた。更に、ボリュームが減ってきたと気にしている頭頂部の髪が、ふさふさとしている。
いやそれどころか、男前だともてはやされた二十歳前後の顔が、シワもシミもない張りのある肌と共に、目の前に在った。
歯磨き粉の隣に置かれた安いデジタル時計を覗き込む。午前二時半の出来事だった。
眠気が吹き飛んでしまったから、ベランダに出て煙草を一本吸った。四月に入っても、夜中はまだまだ寒く、今夜は風も強い。もう見頃の終わった薄ピンクの花びらが、どこからか舞ってきた。
寝静まった街の灯りを見下ろしながら、色々と考えを巡らせる。考えたところで何も解決はしないのに。
「よしっ」
なぜなのか「機能も若さを取り戻しているか確かめる」という結論に至った。もしかすると思考回路も若返っているのかもしれない。
寝室に戻りベッドの上に座る。躊躇いなくスウェットとトランクスを脱ぎ捨てた。
つい先日五十四才になった私は、セックスは随分とご無沙汰だったし、自分で触ることも無くなって久しい。
それでも、これからしようすることを考えただけで、ハリ艶のある身体に性欲が漲ったのが分かって、心が躍った。
陰茎を握り上下に何度かしごけば、あっという間に芯が通り、硬く大きくなり始める。
頭の中には、二十六才年下の部下、青木を思い浮かべた。ちょっとチャラくて、調子がよくて、指が細くて長い。仕事ができて、どうしてか私には少し冷たい男を。
彼が私をぶっきらぼうに呼ぶときの「山野部長、今よろしいですか?」という、ちょっと掠れた声を脳内で再生した。
想像は瞬く間にヒートアップしてゆく。青木に触られているのを、青木に舐められているのを、青木に挿れられるのを、想像してしごく。
先端からはドロドロと先走りが溢れ出し、ヌルヌルと滑りがよくなった。
「んっ、んぁっ」
小さな声も零れでて「はぁはぁ」と呼吸も荒くなる。そして、あっという間に昇り詰め、大量の白濁を飛ばした。
若返っているせいで、一回出したくらいでは昂った性欲は収まらなかった。
独りで暮らすこのマンションには、スキンはもちろん、ローションも置いてない。それでも、後ろを触りたくて仕方がなかった。
苦肉の策で乾燥肌に塗る為に皮膚科医で処方してもらっている乳液を手にとり、後ろを触る。
きつく締まっている後孔を少しずつ解し、プニっと右手中指を潜り込ませる。中の壁を撫でるように擦りながら、奥へ奥へと指を進めた。
「んぁっ。ぁっ、あぁ……」
気持ちが急いて、じっくりなんて触っていられない。
指を一本から二本に増やしたところで、左の手で陰茎を握り勢いよくしごいた。
「ぁっ、あっ……。んぁっ、イ、イクっ」
ビクビクと身体が震え、また大量に吐精し、それはそれは気持ちが良かった……。
アラームが鳴り目が覚めれば、部屋の中には明るい朝日が差し込み始めている。
昨晩は自慰をした後、ティッシュでおざなりに拭いて、下半身を出したまま眠ってしまったようだ。眼鏡をかけ、丸出しの股間を見れば、だらしない五十代の身体に戻っていた。
この不可解な事象が、確かに自分の身に起っていると自覚してから、私は生活スタイルを変えた。
今までは、帰宅しても何もすることがないからと、毎晩遅くまで会社で残業する日々だった。
その私が急に、定時で帰る為に仕事を切り上げるから、青木も驚き問いかけてくる。
「山野部長、具合でも悪いんですか?」
「いや、ちょっと用事ができてね」
そう答えれば「へー、珍しいですね」と興味無さそうに返事を寄越す。内心はこれで自分も早く帰宅できると、喜んでいるだろう。
最寄り駅に着いて、馴染みの定食屋でグラスビールを一杯と焼魚定食を食べ、マンションへ帰る。
掃除や洗濯など家のことを少しして風呂に入り、午後九時半には寝室へ行く。スマートフォンを枕元に置き、そのまま眠りについた。
実証実験初日。アラームは午前二時半に鳴るようセットしておいた。
ピピピと鳴る音で目が覚めれば、既に若い身体になっていた。そうなるともう我慢はできない。また部下の青木を思い浮かべ、自慰をする。
柔らかそうな癖毛や、俺よりわずかに背が低いが華奢ではない身体に触れたいと思いながら。
何度か吐精したのち、いつの間にか眠ってしまった。朝、目が覚めれば、やはり五十代の身体に戻っていた。
翌日は午前二時に起きた。
ちょうどアラームが鳴ったとき、一瞬意識が飛んだような浮遊感があり、目を開ければ若い身体になっていた。
そしてまた自慰をする。ドラッグストアでローションを購入しておいたから、後孔も熱心に触り「あおき、あおき」と名も呼んでしまった。中がうねるように収縮し、喘ぎながらイけば、そのまま寝落ちた。
自慰をした翌朝は、疲れも取れスッキリした気分で朝を迎えられる。しかし昼間、部署内で青木を見かけると、自慰の妄想に登場させている気まずさを感じてしまう。
五十四才のおじさんが、二十八才の部下に抱かれる妄想を毎晩しているなんて、本当に申し訳ない……。「いや、違うのだ。あくまで自慰をしているのは二十才に若返った私なのだ」と心の中で己れを正当化するしかなかった。
午前一時半にアラームを鳴らし起きたときには、五十代の身体のままだった。
そのままボケっと、ベッドの上に座って過ごす。なんとなく陰茎を弄ってみても、心も身体も乗り気にはならず、すぐに飽きてしまった。
性欲が枯れているのだ。
二時ちょうどなったとき、目の前が一瞬暗くなり意識が飛んだ。そして、気がつけば若い身体になっていた。
どうやら午前二時に若返る、ということが判明した。
翌日からは元に戻ってしまう時間を探る。
朝五時にアラームを鳴らせば五十代の身体だった。
朝四時のときは少し変な感じがしたが、目が覚めたときには五十四才だった。しかたがないので、まだ真っ暗なベランダに出て煙草を一本吸ってから二度寝をした。
三時のときは若い身体だ。二十才の姿で目が覚めれば、自慰を覚えたての中学生のように、スウェットとトランクを脱ぎ捨て、陰茎を握り後孔を弄ってしまう。
「あおき、あおき」と名を呼び、五十代のおじさんに向けられる青木の冷めた目線を思い出しながら吐精する。
そして気持ち良さを引きずったまま、スヤっと眠る。
三時半にアラームを鳴らした日も、二十才の身体だったから、自慰を始めた。
快楽を求める欲望は増すばかりで、今夜は長く楽しもうとまずは乳首を弄る。ピンク色の突起は、ぷくりと腫れて甘い痺れを誘発する。
後孔もローションをたっぷりまぶした指で、じっくりと解す。
「あおきっ、んっ、ふぁっ、あっ……」
気持ち良さが波のように、どんどん、どんどん押し寄せてきて、妄想の中の青木もより大胆になる。
「うっ、んぁっ。きもち、いい、いい、あっ」
もうすぐイきそうだ、というタイミングで、目の前が一瞬暗くなり意識が飛んだ。
「あっ」と思ったときには、五十代の身体に戻って、吐精しないまま萎えていた。
ぷくりとピンク色だった乳首だって、カサカサに乾燥していた。
時計を見れば朝四時だ。
この検証を繰り返した結果、どうやら毎晩午前二時から朝四時までの二時間だけ、私の身体は若返ることが判明した。
困ったことに、青木との行為を妄想し自慰をしている間に、私にも欲が出てきた。
もともと五十四才の私が、二十八才の青木に想いを告げることは、現実的でないと自覚していた。部長として、部下に仄かな恋心を寄せているだけで、充分に満足だった。
仕事の打ち合わせをする以外に、同じ飲み会に少しだけ参加したり、ときどき喫煙所で目が合ったり、ぶっきらぼうに挨拶されるだけで満たされていた。
けれど、二十才に若返った私だったら、青木に触れることだって夢ではないかもしれない。若返って年下になった私になら、青木も心を許すかもしれない。
きっと青木もゲイだろうと、同類の者として感じるものが、実はずっとあったから。
若返っている真夜中の時間に青木と会う、そんな機会が訪れるとは思えない。それでも部長の権限を使って会社のクラウドにアクセスし、青木の住所を手に入れた。
そこは私のマンションより二駅先。タクシーで二千円程度の距離だった。
その晩、午前二時に自分の身体が若返ったのを確認してから、マンションを出た。
大きな通りまで歩き、タクシーを拾う。やはり思考回路も若返っているのだろう。
二十才の姿で外に出るのは初めてで緊張したが、タクシーの窓に映る顔は自分から見ても男前だ。五十代の私を知っている人に気づかれない自信があった。
だからこそ、青木のマンションの周りをウロウロする、というストーカー紛いなことを実行しようとしているのだ。
■第二話【部下】真夜中、部屋に連れ込む
ひと夜の都合のいい相手を探しに、ときどき顔を出すバーへ出向いたが空振りだった。わざわざ仕事から帰ってシャワーを浴び、着替えてから出掛けたのに。
顔見知りの常連たちと、時間をかけてダラダラと飲んで、愚痴を言い合っていたら終電を逃した。しかたなく線路沿いを一人でトボトボ歩いて帰ってきた。
燻った気持ちが少しもスッキリしないまま、マンションに辿り着いたのは午前三時少し前。空には三日月が浮かんでいる。
エントランスの植え込みに、男の子が所在なげに座っているのが目に留まった。男の子と言っても、未成年ではなさそうだ。二十代前半くらいだろうか。
スマホを触るでもなく、目の前の幹線道路を行き交う車をただ眺めている佇まいが、浮世離れしていた。
まだ酔いが醒めていない俺は、フラフラと近寄って行って声を掛ける。
「なぁ、どうしたの?こんな時間に。誰かを待ってんの?」
男の子は、俺を見てハッとした顔をする。その顔は綺麗に整っていて、大好きな山野部長に少し似ていた。
このところ、心がザワザワとした日々が続いている。山野部長の様子がおかしいからだ。
あの人、いつも遅い時間まで残業をしていたのに、突然、定時で帰るようになった。
最初は体の具合でも悪いのかと心配になったけれど、最近どんどんと肌艶がよくなっている。
毎日が平坦で浮き沈みのない堅実な生活を送ってますって顔をしていたのに、表情が豊かになった。
仕事中、山野部長を盗み見る度に、何かを思い出すような楽しげな顔をしていたり、考え込んでいたり、ポーっとしていたりする。
もしかして、恋人でもできたのだろうか?五十才を過ぎているとはいえ、山野部長は渋くてやさしいから、そんな人が現れたって少しも不思議ではない。
目元にシワの刻まれた眼鏡の横顔を見れば、若い頃はうんとイケメンで、うんとモテただろうと容易に想像できた。
俺は幼い頃に父親を亡くしている。そのせいか、ちょっと枯れた感じのおじさんが大好きだ。
山野部長はかなり理想的で、同じ部署に配属されてから三年間、ずっと想いを寄せている。
二十八才が五十四才を好きになっても、気持ちは仕舞い込むしかない。だからこそ気づかれないよう慎重に、部長のことを目で追ってしまう。
俺がゲイであることを知っている友達は何人もいるのに、おじさん好きだとは誰にも言ったことがない。
小学六年のとき、教頭先生のことが本気で好きで、それをチラっと口に出したときの周りの反応を見て以来ずっと黙っている。
そんなだから今まで年上と付き合った経験は無く、いつも年下とばかり関係を持っている。そして必然的に上手くいかず長続きしないのだが、まぁ仕方がない。
おじさんは付き合うよりも、遠くから眺めて愛でるもの。
万が一にも俺が好いてることがバレぬよう、気を使う日々。山野部長と話しをするときには、どんなに胸がときめいても、できるだけ素っ気ない態度を取るよう心掛けている。
植え込みに座っていた男の子は、小さな声で「人を待っています……」と答えた。
「ふーん。来ないの?その人」
そう聞き返せば、考えこむように首を傾げる。まだ学生だろうか。少し幼さが残っていた。
なのに随分とおじさんみたいな服を着ている子だった。靴も、カバンもこの男の子の持ち物には見えない渋いセレクションだ。髪型だって今っぽくない。
「それはさ、マッチングアプリとかそういう出会い系?」
「え?」
「いや、言いたくないなら、言わなくていいぜ。でも、すっぽかされたんじゃねぇの?」
そう伝えたら、黙って俯いてしまった。
「ちょっと待ってろ」
酔って歩いてくる道中は感じなかったが、夜中はまだまだ気温が低い。マンション脇にある自販機で缶コーヒーを買ってきて「はい」と渡して隣に座る。
男の子はなぜか酷く緊張していて、アワアワしながら受け取ってくれた。僅かに触れ合った指先が冷えきっている。
「その待ち人が来るまで、ずっとここで待つつもり?」
「いや、それは、あの……」
俯いていた男の子は意を決したように顔を上げ、じっと俺の眼を見つめてくる。視力が悪いのか、顔の距離が妙に近かった。
冷たい夜風が吹き抜けたけれど、俺の酔いは醒めないままで。
だから……だから……。
「なぁ。俺、このマンション住んでるんだけどさ、ちょっと寄ってくか?ここ寒いだろ?」
そう誘ってしまった。断られれば「冗談だよ」と笑って誤魔化せばいいと思って。
「え?あっ、はい!」
予想に反した答えが返ってくる。
座っていた植え込みから勢いよく立ち上がったその子は、俺よりも少しだけ背が高かった。
渡してやった缶コーヒーは開封されないまま、大切そうにカバンへと仕舞われた。
エントランスでエレベーターを待ちながら、考える。
この子が待ち合わせをしていたのは、男か女か。俺の勘では男だと思うし、俺をそういう目で見ていると熱を感じた。
エレベーターに乗り込み、五階に上がるまでの短い時間、試すようにフワっとしたキスをしてみる。身体をビクっとさせ固まってしまったけれど、嫌がる素振りは全くない。
むしろ顔を真っ赤にしながら、俺の手首を掴んできた。
やっぱりこの子、山野部長に顔も雰囲気も似ている。部長の二十才の頃は、きっとこんなイケメンだっただろう。
そう思うと、燻っていた欲にメラメラと火が着いた。
エレベーターが五階で開いた瞬間、肩を抱き寄せ、自分の部屋の前までズンズンと連れていく。
ガチャガチャと鍵を差し込んでドアを開け、もつれるように玄関に入り込み、唇と唇を合わせる。
若いし、大した経験もないだろうと思った。なんなら初めてかもしれないと。色々教えてやりたい、なんて年上ぶった優越感を感じながら、唇を割って舌を潜り込ませる。
彼の口の中は熱く、舌が俺を待ち構えていたように絡んできた。
ハムっと唇を喰んできて「んぁっ」と息継ぎをするように小さな声を溢す。角度を変えては何度も何度も舌を絡め合い、深いキスをした。
キスをリードしていたのは、明らかに俺ではなく、このトロンとした眼になった男の子の方だった……。
「ベ、ベッドへ行こう、な?」
息を切らしながらそう訊くと、コクリと頷いてくれた。
「オマエ、名前は?」
玄関で靴を脱ぎ散らかしながら問えば、一瞬言い淀んだけれど「……リョウ」と教えてくれる。山野部長と名前まで似ている。あの人の名は「良一郎」だ。
「何才?」
「ハタチ。……アナタのことは、なんて呼べばいいですか?」
俺も一瞬迷った。そもそも家を知られた訳だし、表札の「青木」って文字だって見られただろう。
それでも「響一」という名を伏せて「ヒビキ」と名乗った。
ベッドを前にしてしっかりと抱き合えば、リョウの股間は硬く大きくなっていて、ゴツゴツと俺の下腹部に当たる。
それを確認すれば、俺だってあっという間に昂ってしまう。
「俺が抱くほうでいい?」
耳元で囁いて確認すれば「はい」と頷いてくれた。ガチャガチャとベルトを外してやり、ズボンを脱がしてやる。
履いていたのは、やっぱりおじさんみたいなストライプ柄のトランクスだったし、靴下もおじさんしか買わないような代物だった。
それでも清潔感はあるし、肌はピチピチとしていて、なんだかとてもちぐはぐな子だ。
トランクスの上から、大きくなった陰茎を揉みしだけば、気持ち良さそうに腰を揺らす。
「リョウ……」
名を呼んで首筋にキスを落としてから、ベッドに押し倒した。
俺もジーンズを脱ぐ。Tシャツも脱ぎ捨て、ゴムとローションを取り出すために、ベッド脇の引き出しを開けた。
久しく恋人と呼べる人はいなかったから、ローションは買い足されていなくて、残りわずかだった。ゴムは箱があったのに中身は空っぽだった。
「リョウ、ゴム持っている?」
ブルブルと首を横に振る。あー、しくじった。
「悪い。ゴム無かった。中、挿れないから、続けてもいい?」
コクリコクリと頷いてくれた。互いにこんなところで止めるなんて、無理な話だ。
「気持ち良くしてやるから。な?」
シャツのボタンをはずしていけば、中におじさんみたいな白い肌着を着ていた。
それを捲り上げ、ヘソから上に向かって、チュッチュッとキスを落としていく。
胸までたどり着き、ピンク色にぷっくりと膨れた左側の乳首を口に含み、舌で転がすように舐めた。
右側は指でつぶすようにコリコリと弄る。
リョウは気持ち良さそうに顔を赤らめ「ふぅふぅ」と甘い息を吐く。感じやすい体質なのだろう。口が半開きで蕩けた表情が可愛い。
トランクスには、早くも先走りで濡れたシミが出来ていたから、するりと脱がしてやった。
ローションを手のひらに垂らし中指に絡め、後孔の入り口を撫でるように触る。
プニュっと指を入れれば、普段から自分で触っているのがよく分かるくらい、柔らかかった。
「んっ」
「気持ちいい?」
「んぁっ」
奥へ奥へと指を進めれば、潤んだ目で俺を見つめてくるから目尻をペロッと舌で舐めた。
リョウのイイ場所を探しだす為に、指を二本に増やし中でグリグリと蠢かす。
リョウがビクっと身体を反らせる箇所があり「ここ好きなの?」と聞きながら、執拗にそこを攻める。
「ア、ヒ、ヒビキさん、あっ、あっ、いい、いい...」
リョウの中の粘膜が俺の指に纏わりついてくるから、俺も興奮し「はぁはぁ」と呼吸が荒くなる。
リョウは我慢ができないのか、自分のモノを握り上下にしごき出した。
「いいよ、イッて」
そう声を掛け、指を激しく動かせば、リョウの喘ぐ声がグッと大きくなる。
「んぁっ、あ、イイっ、あっ、きもち、いい、いい、あっ」
中がうねるように収縮して、リョウのモノから勢いよく白濁が飛び散った。
「リョウ、四つん這いになって」
まだ「ふぅふぅ」と息が整わないリョウに手を貸し、姿勢を変えさせる。
「足、しっかり閉じて」
股の間に自分の陰茎を突っ込み、擬似的なセックスをする。きっちりと閉じられたリョウの間を、俺の硬くはち切れそうなモノが、出たり入ったりを繰り返す。
「リ、リョウ」
俺の先走りとリョウの後孔に塗りたくったローションのせいで、ヌルヌルとよく滑った。
「あっ、んぁっ、いい、う、うらが、こすれて、あっ、きもち、きもち、いい、あっ」
リョウの掠れたイヤらしい声と合わせ、グジュグジュと擦れる水音が部屋に響く。
「あっ、だめ、あっ、また、またイっちゃう、ヒ、ヒビキさん、あっ、イ、イクっ」
リョウが背中をのけ反らせたとき、俺も堪らず吐精した。
狭いシングルベッドで、二人並んで天井を見上げる。ほんの一時間前に偶然出会った男と、こんな風にやる経験が、今までも無かったわけではない。けれどそうした行為には、虚しさが付き物だった。
不思議なことにリョウとの行為は、まるで何年も前から想い合っていたかのように、心が通じ合えたと錯覚できた。
そんな訳がないのに……。まだ酔いが醒めていないのかもしれない。
「リョウ、そんなにしたかった?誰でもよかった?」
そう聞きながら、頬を撫でてやる。
うつらうつらしているリョウは、その質問には答えず俺の髪へ手を伸ばし「ヒビキさん……」と幸せそうに名を呼んでくれた。
どうして今夜偶然あったばかりの俺を、そんな愛おしそうな眼で見てくれるのか。
「寝るといいよ。俺も八時までは眠るからさ」
そう告げれば「はい」とまだ腹の奥に気持ち良さが残っているような顔をして、ゆっくり目を閉じた……。
あぁ、やっぱり最後までやりたかった。そしたら互いにもっともっと満足できただろうに。
一瞬の静寂ののち、リョウが飛び起きる。
「えっ、ナニ?ビックリしたっ!」
「今、何時ですか?」
「うん?あと十分で四時。八時まで四時間は眠れるぜ」
「え、あっ、ごめんなさい。俺、もう帰らないと」
急に慌て出したリョウは、バタバタと脱ぎ捨てた洋服を書き集め、シャツに腕を通す。
「ヒビキさん、また会ってもらえますか?」
そう言ってくれたから、メッセージアプリのIDを交換しようとすると「あ、それは今は無理で」と口籠る。
理由を聞こうとしたけれど「とにかく、もう帰ります」と玄関で大慌てで靴を履いている。
「じゃあさ、会いたくなったらインターフォン鳴らして。ここ503号室だから」
「真夜中でもいいですか?」
「うん?あぁいいよ。待ってる」
「はい、必ず」
「リョウ」
呼び止めて、チュッと触れるだけのキスをすると、嬉しそうに、はにかんでくれた。
「おやすみなさい」
バタンとドアが閉められた。
ベランダに出て、上から手を振ってやろうと思った。
なのに、エントランスから出てきたリョウは、上を見上げることもなく、走って路地を曲がって行ってしまった。何をそんなに急いでいたのか。
「リョウ、ゴム買っておくからな!」
ベランダから叫んでみたけれど、聴こえたかは分からない。
スマホを見ると三時五十七分で、俺はそのままベランダで煙草を一本吸った。
部屋に戻れば、さっきまで事に及んでいたベッドに、リョウの痕跡と丸まったティッシュが残っていた。
■第三話【部長】淫らな深夜の逢瀬
青木の住むマンションの植え込みに座って、道ゆく車のライトを眺めていた時には、まさか会えるとは思っていなかった。
それでも万が一会えたら、時計と眼鏡で私だとバレる可能性があるのではないかと心配になり、両方を外しカバンに仕舞った。
視力は酷く悪いわけではなく、眼鏡無しでも困りはしないがくっきりとは見えない。
だから青木の部屋に入れてもらって、セックスまがいのことをしている間、輪郭がいつもよりぼんやりと柔らかく、夢で見る世界にいるようだった。
五十四才に戻った帰りのタクシーの中で、常温になった甘ったるい缶コーヒーを飲みながら、コンタクトレンズを買いに行こうと考えていた。
自宅マンションに戻り、眠れたのは三時間弱だった。明らかな寝不足だが、一晩が経った青木がどんな顔をしているのか早く見たいと思えば、身体が動いた。
机に着席する時、ごく普通に「おはよう」「おはようございます」と挨拶を交わす。当たり前だ。青木にしてみれば、昨夜私に会ったという認識はないのだから。
昼前、名古屋の本社から電話があった。長々とした要件を聞いている間、青木のところに経理の若い女性が来て、親しげに話をしているのが見える。
女性はあからさまに青木に気があり、スキンシップがやたらと多い。
なんとなくイライラし、何よりそう思ってしまった五十四才の自分が恥ずかしく、電話を切った直後にトイレに立つ。
トイレで用を足した後はそのまま誰もいない喫煙所に行き、一服しながら昨晩いや、今朝のことを反芻した。
股の間に挿れて擬似的にするセックスなんて、学生の頃に一度経験があるだけだった。
擦れる感触を事細かに思い出しても、五十四才の身体はピクリとも反応しない。それでも気持ちは高揚し、深夜に若返るこの事象がいつまでも続いてくれることを祈った。
ちょうど一本吸い終わったタイミングで、青木が喫煙所に来たから私はもう一本火をつけた。
「雨が降りそうだね」
黙っているのも気まずく、話しかける。
「そうですね」
相変わらず素っ気ないし、会話も続かない。
そんな青木が眠たそうに大きな欠伸をした。つられるように、私も大きな欠伸が出る。若返っている際に体力を使っても、五十代に戻った時その疲れは残っていない。けれど睡眠時間は、足りないままのようだ。
「あれ、山野部長も青木も寝不足ですか?」
喫煙所の前を通りかかった青木の同期が、声を掛けてくる。
「うるせー、遅くまで仕事してたんだよ」
青木がそんな白々しい軽口を叩くから「お疲れ様」と愛しい部下の肩に触れ、一足先に自分の机へ戻った。
仕事の合間に、メッセージアプリのサブアカウントを作る方法を検索する。今のままではアカウント名が山野良一郎になっていて「リョウ」としてヒビキとやりとりができないから。
その週の金曜の夜。
定時で帰宅して三時間ほど眠り、シャワーを浴びてから午前一時半に五十四才の状態で家を出る。
時計と眼鏡を外し、代わりに購入したばかりのコンタクトレンズを装着した。いつも使っているスマートフォン以外に、結局リョウの為にもう一台購入したピカピカの新機種も持った。
しかし大通りに出てもなかなかタクシーが捕まらなかった上に、深夜の道路工事のせいか道が混んでいた。
タクシーの車内で若返ってしまったら困ると心配になり、二時少し前に「その交差点で止めてください」とタクシーを降りる。ここから青木のマンションまでは、徒歩で十分程度だろう。
エントランスのガラスに自分の姿を映して二十才の姿になっているのを確認し、503号室のインターホンを押す。
普通なら寝ていてもおかしくない時間帯だ。一回鳴らして応答がなかったら、帰ろうと決めていた。
けれど直ぐに反応がある。インターホン越しに「リョウ?」とこちらが名乗る前に訊いてくれた。
「はい、そうです。遅い時間にごめんなさい」
そう伝えたらオートロックが解除される。
エレベーターを上がり廊下を進めば、玄関ドアが開き「いらっしゃい」と笑顔で招き入れてくれた。
「何か食べる?何か飲む?」
青木、いやヒビキは配信で映画でも見ていたようで、リビングのテーブルに置かれたノートパソコンからは海外の映像が流れ続けていた。
「いいえ」と首を横に振る。
「映画、一緒に見る?」
また首を振る。
「そう。じゃセックスする?」
コクリと頷いた。
本当はゆっくり話をしたかったし、どんな映画を見ていたのか気になったけれど私には時間がない。
ヒビキはノートパソコンをパタンと閉じた。
「だよな。俺もそうしたかった。ゴムもローションも買っておいたから」
そう言って一歩二歩と近づいて背中に手を回し、ギュッと抱き寄せてくれた。
先日の夜は、キスの時つい私からグイグイと舌を絡ませてしまった。
未成年の頃からずっと、自分より経験の浅い年下としかセックスしたことがなかったから。挿れられる側なのに、年上ぶってリードしてばかりいたのだ。
今回だって青木より私の方が経験があるだろう。けれど、ヒビキにとってリョウは年下の男の子だ。だからもっと身を委ねて、してもらうべきなのだ。
受け身で受け身で、と自分に言い聞かせる。
ベッドに押し倒されキスをされれば、ヒビキの舌が唇を割って潜り込んでくる。
もたらされる快楽を全て受け入れようと全身の力を抜けば、早くも甘い痺れを感じ腰を捩ってしまう。溶かされたいトロトロに。身も心も。されるがまま、舐められるがまま、身体を投げ出す。
舌がピチャピチャと耳を舐め、首筋を這い、喉仏を通って胸を伝う。
指で摘まむように乳首をコリコリと弄られば「ぁっ」と早くも濡れた声が零れた。
今こうしてセックスしている身体は二十才でも、五十四才の頭脳は知っている。嬌声で伝えるという術を。とてもイイことを、気持ちがイイことを、喘いで喘いで伝えたほうが、ヒビキだって気持ち良くなってくれるのだと。
だから、照れも遠慮も無く「あぁっ、んっ、んぅ」と喉を震わす。
ヒビキは「リョウ、気持ちいいの?素直な反応がすげぇ、かわいい」と、太腿の裏を舐めながら言ってくれた。
たっぷりのローションとともに指を後孔に挿れられ、グチュグチュと掻きまわされれば、それだけでイってしまいそうになる。
「早く、早く、挿れて……」
縋るように懇願する。
ヒビキはわざと焦らすように、私の陰茎から滴る先走りを舌先で舐めとってくれた。そして「俺のも舐めて」とイヤらしい声で囁く。
言われるままにヒビキの陰茎を口に含んだ。奥まで咥えたり、浅く咥えたりを繰り返して擦れば、先走りの味が口の中に拡がる。
「んっ、リョウ。リョウは、キスも、うまかった、けど……、舐めるのも、あっ、うっ、うますぎだろっ……」
息を荒くして私の頭を撫でまわしながら、ヒビキが褒めてくれた。
だから、舌で裏筋を刺激しながら搾り取るように口をすぼめ、そのままイかせてあげようとした。切羽詰まって眉が下がって、気持ち良さそうに悶えるヒビキの顔が堪らない。
しかしヒビキは私の口から陰茎を抜く。そしてゴムをつけたかと思えば私の片足を持ち上げて、一息に挿れてきた。
「あっんぁぁぁっ」
繰り返し繰り返し、激しく腰を打ち付けられる。快楽に身体が揺さぶられ「はぁはぁ」と息が荒くなり「ふぁ、んぁっ」と甘い声が零れて。腹の中がヒビキのモノでいっぱいになって、苦しいのに満たされて。
「もっと、もっと、ねぇ、ヒビキさん、あっ、あっ、奥、ねぇ、奥、きもち、いい」
反対の足も持ち上げられ、角度を変えて奥へ奥へと突き上げてくる。
「き、きもち、いい。いい、あっ、すごい、きもち、いい。んぁっ」
「リョウ、リョウ」
名を呼んでくれる。
「ヒ、ヒビキさん、いい、あっ、イっ、イクっ。あぁぁぁ」
自分の腹に白濁が飛び散った。
ヒビキも「んっ」と強く股間を突き上げてきて、そのままゴムの中へ解き放った。
私がまだ中をヒクヒクとさせているうちに、陰茎を引き抜きゴムを外し、新しいゴムに付け替えた。
そして、すぐにまた突っ込んでくる。
「帰らないと」
何度も吐精した後ウトウトしてしまっていたが、気がつけば残り十五分で四時だ。急いで洋服を身に着ける。
「送ってくよ」
そう言ってくれたけれど「大丈夫です」と固辞した。
「ヒビキさん、また金曜に来ていいですか?今日と同じ時刻に」
「もちろん。待ってる」
玄関先でメッセージアプリのIDを交換し、触れるだけのキスをしてもらう。
「リョウ」のアイコンは、うちのマンションから見える朝焼けの写真だ。
ヒビキのアカウントは「aoki」という名で、既に仕事で交換しているものと同じだった。
それからは毎週金曜の夜になると、ヒビキに会いに行った。
念の為、いつも金曜の夕方にメッセージを送信する。それも仕事中の青木がデスクに居るときに。メッセージを送信すると、青木がスマートフォンに手を伸ばし、私の送った文字を眺めているのが見える。
『今夜もおじゃましていいですか?』
青木は画面を見て嬉しそうな顔をするくせに、すぐには既読にしてはこない。しばらくして席を立ち、喫煙所から「待ってる」と簡素な返信をくれる。
真夜中にしか訪ねて来ない理由は訊かないでいてくれた。それでも毎回「朝まで泊まっていけよ」とやさしい声で言ってくれる。
桜が終わり青葉の頃に始まったリョウとヒビキの逢瀬。回を重ねる毎に日の出時間が早くなり、六月の帰路は空が明るい。季節が進むのを実感すると、一体いつまでこうして若返ることができるのかと、不安が押し寄せた。
夜でも気温が下がらず今年初の熱帯夜となった日。事後、脱ぎ散らかした服を身に着けようとすると、ヒビキが「これプレゼント」と紙袋を渡してくれた。
紙袋を開けると、黒をベースにした柄物のボクサーパンツが数枚入っている。
「履いてみて。……うん、似合う、似合う!」
そこで初めてストライプのトランクスでは、おじさんぽかったのかと気がついた。
「ありがとうございます」
慣れない履き心地にモゾモゾしていると「かわいいな、リョウ」と、愛おしそうに抱きしめてくれた。
毎週、毎週、欠かさずに訪ねて四ヶ月が経った。もう夏も終わり、秋の虫が鳴いている。
二人の関係に名前を付けるとしたら「セフレ」なのだろう。恋人同士になれないのは、分かりきっている。それでも、満ち足りていた。
「ねぇ、ヒビキさん。所有の証をつけて」
戯れにそんなことも言ってみる。
クスクスと笑ったヒビキが首元に吸い付き、皮膚がチリチリと痛んだ。
満足そうに私から離れたヒビキは、引き出しから手鏡を出し「ほら」と私に向ける。
首筋には巨峰のような真っ赤な痕が、ハッキリと三つも付いていた。
明日は土曜だから何個付けられても大丈夫だ。けれど月曜にも消えなかったらどうしよう、と五十代に戻った帰りのタクシーで考える。
しかし家に着いて着替えたときには、跡形も無く消えていた。セフレの証など何処にも残せないのだと、思い知った。
仕事では、新しいプロジェクトが始まって、私と青木が組むことになった。
素直に嬉しく張り切って取り組んでいるが、青木は仕事以外の無駄な会話はしてこず、つれないままだ。
再来週の木曜と金曜、名古屋の本社で行われるクライアントとの大きな会議に、東京支社を代表して二人で出席することが決まった。
我が社は本当にケチで、二人で出張のときにはビジネスホテルのツインを用意される。以前の私なら喜んだだろう。青木と同じ部屋に泊まれるのだから。
けれど真夜中に若返ってしまう今、それはピンチでしかない。
あぁ。出張中の二泊三日、どうしたらいいだろう。若返った性欲を抑える心配も、しなくてはならない。
■第四話【部下】淫夢が見せた逢瀬
山野部長と二泊三日で、名古屋の本社へ出張に行くことになった。
その件を部長から聞いたとき、ニヤけてしまわぬよう、とにかく表情筋に力を入れ堪えた。
山野部長は、俺に出張の話をしながら、まるで心配事でもあるかのように眉を寄せた。けれど、そんな表情もまた渋くて格好いいのだから、困る。
俺は出張が決まってから、ずっと機嫌がいい。
金曜にリョウがセックスしに来たときだって、いつもより更にトロトロに溶かしてやろうと、ローションをたっぷり使って入念にほぐした。
トロトロのドロドロになったリョウが、もう我慢できないって顔してピクピクしている状態で「俺のも舐めて、リョウ」と咥えさせる。
「リョウ、リョウ」って名前を呼んで「上手」って髪を撫でながら褒めてやって。
その後、何度も何度も奥まで突き上げれば、リョウは「ヒ、ヒビキさん、すごい、あっ、す、すごい、あっ、いい」とたくさん喘いで縋ってくれる。
相性の良い最高のセックスをすれば、機嫌はもっと良くなるのだ。
もうすぐ朝四時という頃、リョウがいつものように「帰らなきゃ」と言うから「朝まで泊まっていけよ」と、断られると分かっていても引き留める。
背中に抱きつきながら「なぁ、帰るなよ」と耳元で囁いて。それでも、やっぱりリョウは帰ってしまう。
玄関で「来週はさ、木金土が出張になっちゃって、会えないんだ」と伝えた。
リョウは少しだけ考えて「じゃ、水曜の夜に来てもいいですか?」と言ってくれた。
「待ってる。早く来れるなら、夕飯を一緒に食べようぜ?」
そう誘ってみたけれど、リョウはやっぱり首を横にふる。
「いつもの時間に来ます」
「そっか。分かった」
チュッと触れるだけのキスしてをして、玄関先でリョウを見送った。
水曜の夕方。仕事中にリョウから律儀なメッセージが届いた。
『約束通り、今夜おじゃましていいですか?』
スマホを持って喫煙所に行き『待ってる』と返信を打っていると、山野部長も煙草を吸いにやって来た。
「青木、明日はよろしく頼むな」
「はい」
「一緒に出張するの、初めてだな」
「はい」
すこぶる機嫌が良い俺は、ふてぶてしいフリをするのも忘れ、何か気の利いたことを言ってポイントを稼ごうとしてしまった。
「山野部長、明日は新幹線で朝飯ですよね?俺、美味いサンドイッチ屋を知ってるので、部長の分も用意しますよ」
山野部長は俺が予想したより遥かに大袈裟に「それは楽しみだ!」と喜んでくれた。俺はなんだか恥ずかしくなって、自分で言い出したくせに冷めた目を向けてしまった。
その日の深夜、約束通りにリョウが訪ねて来てくれた。
リョウはいつもに増して、貪欲に俺を求めてくる。もうすぐ三十才とはいえ、俺の性欲も衰えていないほうだと思っているが、二十才のリョウの若さには勝てない。
「もっと、ねぇ、ヒビキさん、もっと、もっと。んぁっ、ねぇ」
「どうした?リョウ。足りたい?」
ブルブルと首を振る。
「金曜、会えないから。性欲を、使い果たして、おきたくて、あっ」
どういう意味で言われたのか分からないが、俺以外とはしていないのだと思え、うれしかった。
そして、リョウは俺だけを見ていてくれているのに、自分は山野部長との出張を楽しみにしていることに、少しだけ罪悪感を感じた。
翌朝の新幹線で部長は、俺の用意したサンドイッチを「美味い、美味い」と喜んで食べてくれた。
そして寝不足なのか、食べ終わればすぐに眠ってしまった。
俺も朝四時まで、リョウとセックスしていたのだから眠くて当たり前。名古屋に着くまで爆睡してしまう。
出張は順調だった。山野部長がプレゼンをし、俺が数字を読み上げる。クライアントも何度か前向きな質問をしてきて、いくつかの返事を翌日に繰り越した。
本社で東京支社と連絡を取り、保留にした分の解答を導きだして、夜遅くまで追加の資料を作成した。
夕飯は本社の会議室で、用意された弁当を食べた。
夜遅くになってからホテルにチェックインし、山野部長が先にシャワーを浴びる。
なんとなく気まずく、俺は一階のロビーにある喫煙所に行く。何本か煙草を吸って戻れば、部長はもうTシャツとスウェットに着替えベッドの上にいた。
俺も疲れていたから、山野部長に変な目を向ける余裕もなくシャワーを浴び、すぐに眠りについた。
ふと真夜中に目が覚め山野部長のベッドを見ると、頭からすっぽりと布団をかぶっていて寝姿は見られなかった。
でも、ふくらはぎから先だけが布団からはみ出している。
薄暗い中で見えた足首が妙に色っぽく、とても五十代には見えない。まるでリョウの足のようで、昨晩を思い出しムラムラっとしてしまう。
我慢ができずその足を見ながら、山野部長を抱くことを想像し自慰をした。
ベッドの上で丸くなり、起こしてしまわぬように声を殺す。乱れた呼吸を抑え込み、音を立てないように自分でしごく。
イきそうになって、慌ててヘッドボードのティッシュケースに手を伸ばす。ティッシュの上に白濁を出せばスッキリとして、すぐにまた微睡がやってきた。
朝起きると山野部長は、もう着替えも済ませていた。ギリギリまで眠っていたのが恥ずかしくて「すみません」と謝る。
「いや、いいんだ。年を取ると早起きでね」
俺を悪者にしないよう、スマートに笑ってくれる。
先にホテルのレストランに朝食を食べに行った部長に追いつくために、急いで支度をする。
ふと、昨晩の自慰に使ったティッシュを無造作にゴミ箱に捨てたことを思い出し、部長のベッドと俺のベッドの間に置かれた小さなゴミ箱を覗いた。
ティッシュゴミは、まるで何度も吐精したかのように、大量に捨てられていた。こんなに何度もした覚えはないのに……。
プレゼン二日目も、問題なく終わった。クライアントも提示した内容に納得してくれ、プロジェクトは軌道に乗ったと言っても過言ではない。
夜は、社長がセッティングしたクライアント接待に、駆り出される。社長は飲みの席が大好きなのだ。
俺はできる限り飲んでるフリだけをし、アルコールを摂取する量を控える。山野部長がそれに気がつき、小声で「飲めない人だっけ?」と訊いてくれた。
「俺、短い時間でたくさん飲むと記憶が飛ぶタイプなんです。失礼があったんじゃないかって後から心配になるのが嫌で、こういう席では飲みたくないんです」
部長は、やさしく微笑んで「分かった。無理しないで」と俺の肩を叩いてくれた。
機嫌良くクライアントが帰り、社長と、社長の息子と、山野部長と、俺だけでもう一軒行くことになった。
社長馴染みの次の店へ歩いて移動している時、部長が話しかけてくる。
「どれくらい飲むと記憶が飛ぶの?」
「量は体調によってですけど、短い時間に立て続けに飲むのがダメで。周りが言うには、俺、途中から笑い出すらしくて。そしたら危険信号なので止めてもらえますか?」
「わかった。俺が責任を持ってあげるから」
山野部長は、やっぱり渋くてやさしくて格好いい。
だから俺は、注がれるままにアルコールを摂取してしまった……。
ホテルに戻った時点で、とっくに日付が変わっていたのは覚えている。ベロベロになって山野部長に肩を借りて、部屋まで戻ったのもなんとなく記憶にある。
部長が一瞬リョウに見えて「リョウ?」って訊いたら「誰だいそれは?山野だよ」と答えてくれた。
その部長が、部屋の冷蔵庫からミネラルウォーターを出して口に含んだ。そしてそのまま俺に唇を重ねてくれるから、冷たい水が喉を流れ落ちた。
驚いている間に、その行為は深い口付けへと変わる。唇を喰み、舌を絡ませ、口内を舐められる。それはまるで、リョウのキスだった。
リョウはいつも積極的にキスをしてくるくせに、途中でセーブするように受け身になる。
年下ぶるとでも言えばいいのだろうか?遊んでると思われたくないのか、リョウは俺にリードさせようとする。
山野部長のキスもそれと同じだった。だから「リョウ?」と目を凝らすけれど、当たり前にそこにいるのは部長だった。
俺、やっぱり酷く酔っているのだろう。
「酔ってるみたいだ」
声に出して言えば「夢だよ、青木。いや、ヒビキさん」と目の前にいる部長が、リョウに変わっていた。
なんだ。やっぱり夢だったのだ。
「……リョウ」
裸でベッドに仰向けになっている俺の陰茎を、リョウが咥えている。
そして、いつの間にか用意されたローションをドボドボと手に垂らし、自分で後孔を弄っているのが視界に入る。
グチュグチュと水音がして、リョウの顔は紅く上気している。「あっ、あっ」と声が溢れて、俺の陰茎を舐める作業がどんどん疎かになる。
「リョウ」
夢の中のリョウに話しかければ「ヒビキさん」と甘ったるく返事をくれた。
隣のベッドを見れば山野部長の姿はなく、誰も眠っていない。さすが夢だ。色々と都合がいい。
夢の中のリョウが「あんなに飲ませちゃったから、勃たないんじゃないかと思ったけどよかった」と言う。
そしてボクサーパンツを脱ぎ、俺に跨ってくる。
俺は頭の片隅で、リョウが履いているボクサーパンツはいつか俺がプレゼントしてあげたものだ、と思い出している。
リョウは自分の後孔に俺の陰茎を充て、ゆっくりと腰を落としてきた。俺の硬く滾ったモノが、ズブズブとリョウの身体に埋もれてゆく。
「んぁっ、入って、く。あっ、んぁっ、いい、んぁっ」
リョウは嬌声を漏らしながら腰を揺らす。
ワイシャツを着たまま、緩めたネクタイ姿のリョウの腰に手を当てれば、良さそうにビクビクと震えているのが伝わってきた。
ん?ワイシャツにネクタイ?
夢の中のリョウは、山野部長のネクタイを締めているのか。そう思うと、より興奮した。
俺の上で腰を振るリョウも眼福だったけれど、辛抱できずクルッと体勢を変えて押し倒し、奥へ奥へとガンガン突き上げた。
「あっ、あっ、ヒ、ヒビキさん、あっ」
「リョウ、俺のこと、青木って、青木って呼んで」
「あ、あおき、あおき。いい、きもち、いい、あっ、んぁっ、奥、あっ、あおき」
「ぶ、部長、山野部長。んっ、部長の中、すごい、熱い、いい」
リョウの中がうねり、俺のモノを強く締め付けてくる。
「あおきーっ、イ、イクっ」
「部長ーっ、お、おれも、でるっ」
俺の下でふぅふぅと、まだ息が整わないリョウの顔には、見慣れた部長の眼鏡が乗っていた。
なんて都合のよい夢だろうと、可笑しくなる。
朝。目が覚めると、昨日と違って部長はまだ眠っていた。
慌ててゴミ箱を確認すると、空っぽだったから胸を撫で下ろす。
よかった、やはり夢だったのだ。リョウがここに来るはずはないのだから、当たり前か……。
ホテルのレストランで朝食を食べながら山野部長に「俺、昨晩の記憶がなくて……。失礼はなかったですか?」と確認した。
「大丈夫だったよ。ホテルに戻ってからは、いい夢でも見てたのかい?幸せそうな寝顔だった」
恥ずかしかったから「それも覚えていません」と答えれば、なぜか山野部長が照れたように目を逸らして俯いた。
やはり俺は、昨晩何か言ってしまったのだろうか?
山野部長は社長の家に呼ばれているというので、俺は一足早く新幹線に乗って東京へ帰った。
車内からリョウに『なにしてるの?』と珍しくメッセージを送ると『昨日、ヒビキさんの夢を見ました』と、可愛らしい返信が届いた。
■第五話【部長】忘れ物で身バレの危機
名古屋での出張の夜を、青木は夢だと信じ疑っていないようで助かった。
さすがに、酒を飲ませ午前二時を待ちセックスに持ち込むなんて、羽目を外しすぎていたと深く反省している。
青木が私のことを「リョウ」ではなく「山野部長」と呼んだことも、私に「青木」と呼ばせたことも、酒のせいでおかしな夢を見ていたからだろう。
それでも私にとって、五十代の自分が青木に抱かれるという擬似体験ができたことは、大変な幸せだった。
仕事での青木は、以前より少し踏み込んで私を頼ってくれるようになった。懸案事項は面と向かって納得するまで話し合い、部長と部下としてよい関係を築けているように思う。
リョウとしても、季節が進んで街路樹が色付いてきた今も、毎週金曜の真夜中に変わらずヒビキを訪ねている。
マンションのエレベーターを上がれば、玄関でヒビキが待ち構えていて、抱きしめ深いキスをしてくれる。
少しの時間も無駄にしたくなく、キスをしたまま靴を脱ぎ、いつもならそのまま縺れるようにベッドへと雪崩れ込む。
けれど「今日はこっち」と広くはないリビングのソファへと誘導された。
ベッドだろうとソファだろうとやる事に変わりはなく、少しずつ脱がされ、舐めたり舐められたりして、二人とも真っ裸になった。
ただ、いつも常夜灯のみの寝室と違ってリビングは煌々と明るい。そして何故なのか、今夜はいつもよりたっぷりと時間を使って事が運ばれている。
「リョウ。顔、見せて。こっち向いて。ほら、そのトロけそうな顔、すげぇかわいい」
頬から顎をヒビキの指先が辿り「肌も綺麗だな。シミ一つもない。若々しくてツヤっとしてる」と眺められる。
確かに自分でも見惚れるほど、二十才の身体は美しく鑑賞に値する。しかし今褒められたのはあくまでリョウ。私自身がとうの昔に失った物。だからヒビキの言葉に、リョウへの嫉妬が顔を出す。
「見た目なんて、褒めないで……」
「なんで?美しいよリョウは。自信持てよ」
違うのだ、と首を横に振るその姿にも、ヒビキは「かわいい」と言って、キスをしてくれた。
そしてヒビキは、寝室から予め持ってきてあったのだろうローションを手に取り、後孔を指で探る。私が悶える箇所を的確に心得ている彼は、指だけで快楽をもたらしてくれる。
「ヒビキさん、あっ、ヒビキさんっ。指、きもち、きもち、いい、あっ、そこ、ねぇ、あっ、いいっ」
きっとさっきより、ずっと蕩けた顔をしてしまっているだろう。中に入る指の数が増えれば嬌声も大きくなり、気持ち良さの波にザブンザブンと飲み込まれてゆく。
しかしヒビキは、これ以上の行為に進もうとしなかった。指で中を掻き回し、反対の手で胸の突起を弄って、時々内腿にキスを落とす。その繰り返しだ。
「ヒ、ヒビキさんっ、挿れて、もう、挿れて、ほしい、ねぇ」
はしたなく懇願するしかなく、腰を揺らしてその先の行為を催促する。
けれどヒビキは「かわいい、リョウ」と微笑むばかりだ。ヒビキの股間だって先走りで濡れ、酷く興奮しているのが見て取れるのに。
指を抜き差しされ、粘膜が擦れる刺激だけで達してしまいそうになる。
「ダメっ。あっ、もう、もう、指、指だけで、イク、イッちゃう」
意地悪なことに、ヒビキはそこで指を抜いてしまった。
「ど、どうして?」
昂まった快楽のやり処が無くなり、ピクピクと身体を震わせる。行き場を失った熱い感情が一筋の涙として流れ出た。
「あっ、ごめん。ごめんリョウ。ちょっと意地悪した」
涙に慌て謝ってきたヒビキは私を掻き抱く。彼の硬く大きくなっているモノが、下腹に当たる。
「俺だってもう我慢できないよ。でもさ、リョウは終わったらいつも帰っちゃうじゃん。だから、朝までこうして焦らしてたら、ずっと居てくるかもって思ってさ……」
ヒビキはもう一度「ごめんな」と口にした後、ソファの上に寝そべる私の足を持ち上げ、一息に貫いてきた。
そのまま奥へ奥へと強く突き上げられれば、指の先までも痺れるように気持ちがよく、嬌声が止まらない。
「もっと、ねぇ、もっと。あっ、んっいい、いい」
「中、すごい、うねっている……。リョウ、リョウ!」
ヒビキは体勢を変え、更に奥へ奥へと打ちつけてきた。
「イクっ、あっ、イっちゃう、あーーーー!」
共に果てても、私はいつまでもいつまでも腹の中が気持ちよく、包むように抱きしめられながら「ん……」と悶え続けた。
ヒビキは狭いソファの上で小さな子にするように髪を梳いてくれながら、ウトウトと微睡む私に「な、もう一回しよ」と呟いた。
頷きそうになったけれど、リビングの壁にかかった時計を見上げれば、そんな時間は無かった。
「もう一回してさ、泊まっていけよ。朝になったらモーニング食べに行こうぜ。そんで一緒に映画を観よう。そういうのもいいだろ?」
ヒビキが耳元で囁いてくれるけれど、弱々しく首を横に振ることしかできない。
あぁ、この二十才の身体が昼まで続き、そんなデートができたらどれだけいいだろうか。
いや本心は、部長として青木とそんなデートをしてみたい……。
ヒビキの家を出たのは、四時五分前だった。
玄関まで見送りに出てくれたヒビキと別れを惜しむこともできずに、大慌てで五階からエレベーターに乗りエントランスから外へ出る。
小走りで大通りから路地に入り、人気のない住宅街を進む。コンビニの前に置かれたゴミ箱の前で立ち止まって、自分のスマートフォンを見た。
四時一分前。辺りはまだ真っ暗で見上げれば細い細い月が出ている。一瞬意識が飛んだような浮遊感のあと、私は五十四才の身体に戻ってしまう。
溜息をついて、キョロキョロと周りに人がいないことを確認し、着ていたブルゾンを一旦脱ぎ、裏返す。
万が一のことを考え、このリバーシブルのブルゾンを購入したのだ。
コンタクトレンズも、五十四才の眼だと異物感を感じるので、タクシーに乗る前に外し眼鏡に付け替えようとした。
しかし、ブルゾンのポケットに入れていたはずの眼鏡を探すも、見つからない。
もしかして青木の家で脱いだときに、ポケットから落としてしまったのだろうか。
まいった。どうしよう……。
五十代に戻り身体は睡眠を欲しているが、二十代と地続きの心は焦っている。とにかくコーヒーでも飲んで頭をスッキリさせ、対策を考えねば。
そう思いコンビニに入り、テイクアウトのコーヒーを購入した。
コーヒーマシンから紙コップに熱々の液体を注入しながら、眼鏡のことを考える。
すぐにメッセージを送って「忘れ物をしてしまったんです」と伝えるのも、眼鏡の存在を印象付けてしまう気がして得策ではない。
青木は私の眼鏡のデザインなど覚えていないだろうが、万が一ということもあるのだから。
明日の真夜中、また青木の家を訪ねようか。それとも、眼鏡のことは全く触れないようにして、新しいものを購入しようか。
青木はもう忘れ物の眼鏡に、気が付いただろうか?
ひょっとしてメッセージが来ているかもしれないと、カバンからリョウのスマートフォンを取り出し、通知を確認しようとした。
片手にコーヒーを持って、コンビニの自動ドアを通り抜けながら。
ドスン。
店を出たところで、目の前の道を走ってきた人とぶつかってしまった。人の少ない、まだ真っ暗な時間帯なので油断をしていた。
持っていたコーヒーが自分にかかり、咄嗟に「熱っ」と声を出す。
ベージュのズボンにコーヒーの染みができてしまったが、自業自得だから詫びるのは私のほうだ。
「申し訳ない、大丈夫ですか?」
熱さを我慢し顔を上げると、そこには青木がいて「部長?」と話しかけられる。
「え?」
「どうしたんですか、山野部長。こんな時間に、こんなところで。ご近所だったのですか?」
酷く驚き、しどろもどろになってしまう。
「あ、青木……。青木こそ、こんな時間に……どうしたんだい?」
「ちょっと人を探していて」
「真夜中に?」
「いや、あの、友人が忘れ物をしたので、届けようと……」
私は大きく息を吸い込んだ。
「青木の家はこの辺りなの?」
白々しく訊く。
「えぇ、あぁ、そうなんです。よかったらうちに寄って、コーヒーの染みを拭いたほうが……」
「いやいや、こんな時間に申し訳ないよ。それに友達を探していたんだろ?」
「大丈夫です。アイツ急いでいたみたいだから、きっと追いつかないし」
断ろうと思った。話をややこしくするべきではないと。
しかし青木が「部長、今日は眼鏡じゃないんですね」と、意味深に私の顔を覗き込むから、狼狽えてしまう。
だから「寄っていってください」という言葉に押し切られ、青木のマンションに行くことになってしまった。
青木の一歩後ろを歩きながら、頭の中で必死に最も良い切り抜け方を考える。
「このマンションの五階です」
十五分も経たず、またこの場所に戻ってきてしまった。
五階に着き、青木が鍵を開け中に入ると、リビングからモワっとした湿度を感じた。
さっきまでしていたセックスのせいだろう。
青木は急いで窓を開け換気をし、落ちていた丸まったティッシュを拾う。
「すまないね。突然、お邪魔して」
「いえ。散らかってて申し訳ないです。今、タオルを濡らしますから、コーヒーの汚れ拭いてください」
私の頭は、どうするのが最適かまだ正解を出せずにいた。
私がズボンを拭いたあと、青木はこぼれてしまったからと、インスタントコーヒーを淹れてくれる。
その隙にこっそり、リョウのスマートフォンの通知を確認した。
『リョウ、眼鏡忘れてる』
『この眼鏡、誰の?』
『知ってる人の眼鏡に似てるんだけど。ていうか知ってる人の眼鏡なんだけど』
『リョウ、どういうこと?』
『今、どこ?』
五件もメッセージが届いていた。ちょうど四時になった頃に送られたものだ。
私は深く深呼吸をして、コーヒーを運んできた青木に話しかける。
「実はね。今、甥っ子がうちに居候していてね」
「甥っ子?」
「そうなんだよ。もう二十才なんだけど、預かってる身としては、フラフラ遊び歩いたりしないように厳しく接していてね」
「あぁ。それで残業せず早く帰宅されるようになったんですか?」
「ん?あっ、そう、そうなんだ」
口からペラペラと出まかせが出てくる。
「その甥っ子がね、ときどき夜中に家を抜け出すんだ」
「え?あっ、はい」
「いや、いいんだよ。もう大人だしね。でも、ほら預かってる身としては気になったから、ちょっと後をつけてきてね。まぁ、この辺りで、見失っちゃったんだけど」
私の言うことを疑っていないだろうか?と青木を顔を盗み見る。
「それで、そのままぷらぷらと散歩をしていてね。真夜中の散歩っていうのも、楽しいものだね」
「はぁ」
「眼鏡もね、その甥っ子が持って出ちゃったみたいで、今日はコンタクトなんだ。たぶん年齢を上に見せるための小道具にするんだろうね。全く困ったものだよ」
こんな嘘で通用するだろうか?何しろ青木は、あれが私の眼鏡だと気がついているのだから。
話をしながら、とてもとても眠くなってきた。壁の時計を見れば四時半だから青木だって眠いだろう。
大きな欠伸を隠し切れずに、大口を開けてしまう。
「部長、始発まで少し寝ていかれたらいかがですか?ベッドのシーツ、今朝替えたばかりですから。嫌でなかったら是非」
断るべきだった。
これが仕事の判断だったら、断る以外の選択肢はなかっただろう。
でも、本当に眠かったから。青木の声が心地良かったから。何より朝までこの部屋に居てみたかったから。
「悪いね。お言葉に甘えて、ちょっとだけ横にならせてもらおうかな」
「よかったら、スウェットに履き替えますか?貸しますよ」
今このズボンを脱いだら、青木がリョウにプレゼントしたボクサーパンツを私が履いていることがバレてしまう。
酷く眠くてもそれは覚えていて、着替えを拒むことができて本当によかった。
勝手知ったるベッドに入れば、あっという間に深く深く眠りに落ちる……。
窓の外から聞こえてくる子どもが泣く声で意識が少しずつ覚醒する。ゆっくり目を開けると、眠っている「ヒビキさん」の顔が目の前にあった。
明るい光の中なのに、こんな体温を感じる距離で会えたことがうれしくて、手を伸ばしそっと頬に触れる。
「ヒビキさん」の手は私の腰に廻されていて、眠りながらもギュっと力を入れて引き寄せてくれた。
時計を見れば、もう昼近かった。随分と長く寝てしまったようだ。それでも私はもう少しこの甘い時間を味わいたくて「ヒビキさん」に擦り寄り再び目を閉じる……。
「え?」
パチっと目を開け、自分の手の甲を見ると、小さなシミやシワがいくつもあった。五十四才の身体だ。
一瞬、この状況が理解できなくて、飛び起きそうになったが堪える。
いや、え?どうしよう。
青木の腕が私を包み込んでいるから身動きも取れない。
まいった。
そう思案しているうちに、青木も目が覚めたのかモゾモゾと動きだした。
私は寝たフリをするために、目を閉じる……。
青木の手が、バっと私の腰から離れた。慌てているのが、目をつぶっていても分かる。
きっと、リョウと間違えていたのだ。自分が抱きついていたのが、こんなおじさんだと分かりショックを受けているのだろう。
そう思うと、五十代の自分が酷く哀れだった。
青木の顔が近づいてくるのが、気配で分かる。なんだろう?観察されているのか?
暖かい息が顔にかかった。見ないでくれ。こんなおじさんのシミとシワだらけのハリのない顔を。そんなにじっと見ないでくれ。
唇に温かく柔らかいものが、フワッと触れて離れていった。
今のはいったい……?
青木はそのまま身体を起こしベッドを離れた。私はまだ寝たふりを続けている。
しばらくするとコーヒーの良い香りがしてきたから、ノロノロとベッドから出た。
「おはよう」
「おはようございます」
「昨晩はすまなかったね。こんな時間まで眠ってしまったよ。青木は、ソファで寝てくれたの?」
「あっ、いや、はい」
「そう。ありがとう。洗面所借りていいかな?」
「どうぞ。置いてあるタオル、使ってください」
鏡の前で何度も何度も自分の顔を見た。
寝る前にコンタクトレンズを外しているからボヤっとして見えるとはいえ、確かにくたびれた五十四才の顔だった。
さっきの青木は、どう見間違えて私にキスなどしたのだろう?
「部長、大丈夫ですか?」
声を掛けられるまで、鏡の前で放心してしまった。
もしも、もしも。青木が私にキスすることに、嫌悪を感じないのだとしたら。私にも少しだけ希望があるのだろうか?
その場合、私のライバルはリョウなのだろうか?
■第六話【部下】久しぶりは風呂場で
リョウが眼鏡を忘れた夜、つまり部長が泊まっていった秋の夜。俺は自分の大胆さに呆れ果てた。
部長は余程眠かったのか、コーヒーの染みがついたズボンのまま俺のベッドに入り、スヤっと寝てしまった。
その寝顔はやはりリョウと似ていて、伯父と甥だということに納得する。近づき、指で頬を突いてみたけれど、深く熟睡していて起きる気配はない。
だから、ほんの出来心を実行に移す。
狭いシングルベッドへ慎重に足を滑り込ませ、添い寝の体勢をとる。身体を密着させたけれど部長の寝息は乱れないから大丈夫。早く目的を達成してしまおうと、手に持つスマホのインカメラで、シャッター音を気にしながらツーショットを撮った。
撮れた写真に満足し、流出させてしまわぬようその場ですぐにフォルダを作り、宝物のように保存した。
ベッドの中は部長の温かみを感じる。顔を寄せればリョウと同じ匂いがした。一緒に住んでいるのだからシャンプーが同じなのだろう。
添い寝で少しだけ触れ合った肌には、年を重ねた柔らかさがあった。リョウにはないシワや眼の下の弛み、白髪が混じった頭髪にいぶし銀の大人の魅力を感じ、元来おじさん好きな俺は股間を膨らませてしまう。
とても眠いのに、この熱を出さないことには入眠できそうにない……。さっきリョウに「もう一回しよ」を断られ燻っていたものが、再熱してしまったのだ。
流石に向き合ってする勇気はなく、そっと寝返りを打って部長に背を向ける。背中に体温と穏やかな呼吸を感じながら、俺は自分の下着の中に手を入れ、息を殺して陰茎を握った。
シングルベッドの振動を気にしながら、上下にゆっくりとしごき始めた。それは出張先ホテルのベッドでした自慰よりも、もっとずっと思い切った行動だった。
乱れた呼吸を必死に飲み込み、音を立てぬように静かに擦る。万が一にも部長が目を覚ましたらどうしようというスリルが、興奮を助長しあっという間に昂まっていく。
「……っ……んぁっ」
達した瞬間、快楽に満ちた呻き声を発してしまった。部長がその声に反応したように、寝返りを打つ。しかしスースーとした寝息は変わらないままだったから、そっとウェットティッシュに手を伸ばし、受け止めた手のひらをおざなりに拭う。
出すものを出せば、急激な眠気に襲われた。窓の外はまだ暗いけれど、もう明け方だ……。少しだけ、ほんの少しだけ、このままこのベッドに居たいと思いながらウトウトする……。
恐ろしいことに、俺はそのまま狭いベッドで部長の温かみを感じながら、寝入ってしまった。
意識が浮上した時には、もう昼に近かった。微睡の中で「あれ?リョウがいる」と嬉しく思う。しかしゆっくり目を開けると、そこには部長の顔があった。更にけしからんことに俺の腕は部長の腰に巻きついていて、驚きのあまり心臓が止まりそうだった。
とにかく、部長より少しでも早く目覚めた自分を褒めてやりたい。
慌てふためく中にも「これはなんと素晴らしい状況なのだ!」と感嘆する気持ちもあった。だから調子に乗って部長に触れるだけのキスをして「これはもう一生の思い出だから」と、自分に言い訳をした。
*
翌週。七ヶ月間ずっと続いていた金曜夕方に届くリョウからメッセージが、来なかった。それでもは夜は、配信で映画を見ながらインターホンが鳴るのを待っていたが、朝になってしまった。
恐らく、夜中に家を抜け出し何処かに行っていることを、部長に酷く叱られたのだろう。
リョウには忘れ物を返せないままで、部長の顔には既に新しいデザインの眼鏡がのっていた。幸い、リョウの相手が俺だとはバレていないはずだ。
その翌週も、リョウからの連絡はなかった。更にその翌週もメッセージは届かない。
リョウに会いたい気持ちはあったけれど、甥っ子思いの部長にバレて悪く思われたくないという考えが強く、俺からはメッセージを送らなかった。
そんなリョウが来なくなった金曜に、なぜか部長が夕食に誘ってくれるようになった。
その誘いはもちろん飛び跳ねる程、嬉しかった。けれど、今まで必死につれない態度を取ってきたのだから、急に路線変更もできない。
部長にしても、一度家に泊めたくらいで俺が急に好意を全面に出したら、気色悪く思うだろう。
だから毎回、できるだけ素っ気なく「別にいいですけど……」と返事をした。
会社の最寄駅で定食を食べながら、それぞれビールを一杯だけ飲む。そして部長が「配信で何か映画を見たいのだけれど、オススメはないかい?」と訊くので、あれが面白かった、これが面白かったという話を熱心にしてしまう。
電車の中で「ご馳走様でした」「お疲れ様、また来週」と別れる。部長と部下らしい真っ当なお付き合いだ。
俺より二つ手前の駅で降りる部長の後ろ姿を、毎回懐いた犬のように尻尾を振って見送っている。
部長との週に一回の食事で心は満たされているものの、冬だから、寒いからと理由をつけなくても、真夜中にベッドで一人、人肌が恋しくなることが多々ある。
どこもかしこもツリーが飾られ、世間がすっかりクリスマスらしくなった曇天の金曜。
意を決して仕事の合間に喫煙所から、メッセージを送った。
『リョウ元気?どうしてる?久しぶりに会いたいよ。とにかく一度連絡して』
自分のデスクに戻り、パソコンに向かいながらも、返事が来てないか何度もスマホ画面を見て確認した。しかし既読にはならない。
寂しく思うも、終業時間には今夜も部長から「雨が降りそうだけど、夕食に付き合ってくれるかい?」と誘いがあったからホイホイとついて行った。
いつもと同じ店で、一杯のビールと定食を食べながら、思い切ってリョウのことを尋ねてみた。
「山野部長。そういえば同居されてる甥っ子は、まだいらっしゃるんですか?」
「え?あぁ、彼ね。うん、いるよ」
「今もまだ夜中にふらふら出歩いているんですか?」
「い、いや、最近は大人しくしているみたいで、助かるよ」
なぜか少し寂しそうに部長が答えた。
俺はリョウが他の男の家に行っている訳ではないと分かり、安心する。
部長には悪いけれど、俺はやはりリョウに会いたい。リョウに情が芽生え、可愛く思っていることを認めざるを得なかった。部長が好きだけれど、リョウとも肌を交えたいのだ。
年上好きの自分がどうしてこんなにもリョウに惹かれるのかは、まるで分からない……。
帰りの電車で部長と別れてから、もう一度リョウにメッセージを送る。『今夜、来てよ』と。
マンションに辿り着いて程なく、リョウからメッセージが届いた。
『スマホを持たずに出かけていて、今見ました!今夜行ってもいいですか?』
もちろんすぐに『待ってる』と返信した。
夜が深まると、窓の外から大きな雨音が聴こえ始める。スマホの天気予報によると真夜中にかけ大雨になるらしい。
寒い冬の冷たい雨の夜に誘ったことを申し訳なく思いながらも、心は弾み、ベッドのシーツを新しい物に取り替えた。
午前二時を少し過ぎた頃、インターホンが鳴る。リョウを迎え入れすぐに抱きしめたかったが、彼はびしょ濡れだった。
「歩いてきたの?」
「道が混んでいて途中でタクシーを降りたから、走ってきました」
なぜ?と思ったが、急いで来ようとしてくれたのなら嬉しい。
「クシュン」とリョウがくしゃみをするから、風邪を引かぬよう「シャワーを浴びて温まったら」と勧める。
リョウは遠慮なのか首を横に振った。
「じゃ一緒に入る?」
「それなら……」
照れたように頷いてくれ、狭い脱衣所で服を脱がせる。
「先にシャワー浴びてて」
そう告げ、リョウの着ていたものをリビングのエアコンの前に並べて、すぐ乾くようにした。
裸になり風呂場に入ると、リョウが抱きつき密着してきた。酷くがっついているのが分かる。それは俺も同じだった。
シャワーの湯を身体に掛けながら、唇を合わせ貪り合う。角度を変え、何度も何度も舌を絡め合う。
「リョウ……、会いたかった」
「我慢、してたから。ヒ、ヒビキさんと会うの、我慢してたから。好きになって、ほしくて、我慢していたから」
シャワーの音が邪魔をして、リョウの言っていることがよく分からない。好きになって欲しいのに、どうして我慢をする必要があるのか……。
リョウは「舐めていい?」と俺の前に跪き、俺の陰茎を持ち咥えた。風呂場はシャワーの熱い湯気でモワモワと充分に温まったから、俺は湯を止める。すると狭い空間に、リョウが口淫するイヤらしい音と息遣いのみが反響した。されている俺よりも、しているリョウのほうが感じているようで甘い声も漏れていた。
濡れた頭皮を撫でてやりながら、リョウのしてくれる行為に酔いしれる。
「だひて」
咥えたままそう言うからコクリと頷き、されるがまま高みを目指す。
「リョ、リョウ、すごく、上手。それ、いい、あっ」
窄めた口で先端を吸い上げられ、更に両手を使って強く擦られ、ひときわ陰茎が大きく膨らみ「イ、イクっ」とその口の中に解き放った。
「はぁはぁ」と息を乱しながらリョウを見ると、恍惚とした顔でゴクリと喉仏を動かし、俺の出した欲望を飲み込んだ。口の端からは、溢れ出た白濁が一筋流れ出て、堪らなく卑猥だった。
リョウに風呂場の淵に掴まるよう指示を出し、尻をこちらに向けさせる。ボディソープを手に取り、後孔をガツガツと解してゆく。
リョウの口からは「んっ、ぁんっ」と甘い声がひっきりなしに漏れた。指を増やし、リョウの身体がビクンと震える箇所を触れば、彼の腰がゆらゆらと揺れる。
空いている手を前に回し胸の突起を弄ると、そこは小さくぷくりの腫れ、陰茎からは先走りがタラリと蜜のように溢れ落ちた。
「もう、もう、挿れてほしい……、ねっ、ヒ、ヒビキさんお願いっ」
そんな可愛くおねだりされれば我慢など効かず、リョウの後孔に再び硬くなったモノを充て、奥まで一息に貫いた。
圧迫感で苦しそうにするリョウを後ろから抱きしめ、耳元にキスを降らせながら馴染むのを待つ。
辛そうだった呼吸が段々と甘い吐息に代わり、中が俺を締め付けるよう蠢いてくる。少し揺すってやれば、あられもない嬌声があがった。
そこからは、ただただ擦って揺すって突き上げて、リョウの中を捏ねくりまわす。
リョウの足がガクガクと力を失うから、腰をしっかりと持って支えてやる。
「あっ、もう、もう、ダメっ、いい、あっ……イ、イっちゃっ」
リョウが達したタイミングで中が強く締め付けられ、俺は彼の腹の中に吐精した。
二人で風呂場のタイルに座り込み、抱き合った。呼吸が落ち着くと段々と寒くなってきて、シャワーでリョウを洗ってやる。
再び後孔に指を入れれば、また良さそうな声を出すけれど「掻き出すだけだから」と言い添え、背中を撫でてやった。
空っぽの狭い湯船にリョウを後ろから抱き抱えるような姿勢で入り、お湯を張る。二人の体積のせいであっという間に湯は溜まった。
ウトウトと寝てしまいそうなリョウを支え、名を呼んでは振り向かせて触れるだけのキスをする。リョウは時々ふふっと嬉しそうに笑う。
風呂から上がり、一旦俺の部屋着を貸しリビングへ移動する。ドライヤーで髪を乾かしてやる作業は、まるで二人で暮らしているかのような幸せな時間だった。
四時二十分前に俺から声を掛けた。
「もう帰らないとだろ?」
コクリと頷く。
すっかり乾いた洋服を身に纏うリョウに「毎週じゃなくてもいいから、また来いよ」と伝える。
時間に余裕を持って送り出したリョウに、眼鏡を返し忘れたと気がついたのは翌朝のことだった。
年が明け、部長との夕食は毎週金曜、リョウとは隔週金曜に会うという、幸せな日々を送っている。
梅の花が咲き始めた頃、社長親子が東京支社へやってきた。
社内会議で部長がした進捗状況報告に社長は満足し、機嫌がよかった。
終業時間と同時に「よし飲みに行くぞ」と部長が誘われている。心の中で「お疲れ様です」と思っていると「青木も行くぞ」と社長の一声で巻き込まれる。
社長の息子が選んだ、女の子が接客してくれる店に連れていかれ、社長がよく飲みよく喋るのをただ眺めていた。
社長はこういう場で羽振りの良い人だし、話も上手いので盛り上がる。ゆえに接客のプロの女性たちにも好かれるのだろう。ビール一杯飲んだ後は、烏龍茶しか飲まない俺とはまるで違う。
何の話の流れだったか、都市伝説の話になった。
「俺も聞いたことあるぞ。五十代の男が、真夜中に二時間だけ若返る病があるっていう都市伝説だろ」
いい大人が何を言い出すのやら、と思ったが接客のプロ達はその話にもきちんと相槌を打つ。
「それって肉体的にってことですか?」
「ああそうだ。髪がフサフサになって、腹も凹んで、肌だってピチピチになるらしいぞ」
「真夜中に?」
「そう、真夜中に二時間だけ。だからその病に罹っても気が付かない男も多いらしい。なにしろ眠ってる時間だからな。気が付けばラッキーだ」
「へー、そんな病ならこのお店に来るようなお客さんは、みんな罹りたいと思うでしょうね」
「五十代の頭脳のまま身体が二十代に若返るんだから、ヤラしいことだってやりたい放題だぞ」
社長が下品に笑って「やだー」と窘められている。
「じゃあ、社長さんも実は真夜中になったら若返っているのかもしれませんね」
「いや俺はね、その話を聞いてからトイレに鏡置いて、尿意で目が覚める度に若返ってないか確かめてるけどダメだね。残念だよ」
こんな荒唐無稽な話、部長も呆れているだろうと並びのソファに座っている姿を横目で見ると、真剣な顔をして聞いていた。部長も若返りたいなんて思うことがあるのだろうか。
さっきまで社長の息子と話をしていた女の子が「私も知っています、その都市伝説」と手を挙げた。
「お客さんに聞いたことがあるんです。その人の知人は、六十近い奥さんに毎晩真夜中にセックスを迫るようになっちゃって、別居されたって」
確かにうっかり若返って性欲が湧いても、中々それを処理することは叶わないだろう。
違う子も言う。
「私、前に勤めてた店のお客さんが「真夜中になると若返るから夜中に会ってくれ」ってしつこく誘ってきて。意味わかんないと思ってたけど、この病だったのかな?絶対嘘だと思ったから、支配人に言って出禁にしてもらっちゃった」
社長は「他人事だと面白いな」とゲラゲラ笑う。
「だけどな、若返りはきっかり一年だけなんだとよ。一年すると、病は突然治るそうだ。若い身体使って味をしめてたら、治った時に立ち直れなくなるな」
「確かにー」
俺もそりゃそうだろと、頷いてしまう。
「更にな、何しろ病だから後遺症が残るんだ」
この話に興味深々の部長が、真剣な顔で身を乗り出し「どんなですか?」と聞いた。
「若返りは一年で終わっちまうのに、若い頃と同じだけの性欲が残るらしい。想像してみろよ、若返っていれば困難であれ相手を探すことは可能だろうよ。でも、年老いた姿で強い性欲だけあったら、ただの変態エロジジイ扱いだぞ」
「うわー、確かに嫌だー」
「たまにいるグイグイ誘ってくるおじ様って、もしかして後遺症に苦しんでる人だったのかなぁ?」
「でも、そんなの同情できないよねー」
「ホントに」
部長が突然席を立った。
「すいません。体調が悪くて、お先に帰らせていただきます」
「おい、大丈夫か?青木送ってやれ」
「いや、大丈夫ですから。少し飲み過ぎたのかもしれません。青木くん、いいから。本当に。君は社長をホテルまでお送りして」
青い顔をして、部長は帰ってしまった。
その後の話題は、社長の家で飼っている大きな犬の話に移り、社長の息子は女の子一人とカウンター席へと移動してしまった。
俺の頭の中は、さっきからずっと何かに引っ掛かっている。
帰り道も、都市伝説の話をグルグルと思い出していた。なんでこの話がこんなにも気になるのだろうか。
電車の吊り革に掴まりながら、窓の外を眺める。
もしかして……。
その可能性に当て嵌めたら、全てが腑に落ちた。
けれどこんな可笑しな都市伝説、簡単に信じることはできない。
だけど、やっぱり、もしかして……。いやそんな、バカな、でも確かに……。
俺とリョウが初めて会ったのは、桜も終わり、青葉が茂る頃だった。それは部長が病に罹って、どれくらい経った時だったのか。
気になり出すと止まらない。
この時点で俺はもう、部長が真夜中に若がっていることを信じきっていた。
部長がいつも降りる駅で電車を下車し、電話をかける。
「あ、青木です。夜分にすみません。ご気分はどうですか?」
「わざわざ電話をくれたのかね?ありがとう。もう大丈夫だよ」
声はいつもより暗かった。
「あの、山野部長。こんな時に申し訳ないのですが、今夜、甥っ子のリョウくんに会わせてください」
「な、なにを突然」
部長は酷く驚いている。
「今から伺ってもいいですか?」
「い、いや、リョウはまだ帰ってなくてね」
部長は慌てていて、リョウと俺が知り合いだということには驚かない。
「今から伺いますから、待たせてください」
「む、無理だよ、すごく遅い時間だよ、あの子が帰るのは」
「それでも会いたいんです」
電話の向こうで大きな溜息が聞こえ、大好きな部長を困らせていることに、罪悪感を覚える。
「……じゃ、本当に来るかい?リョウに会えるとは限らないけれど」
「無理を聞いていただいて、ありがとうございます」
最寄駅からの道順を聞いて、俺は部長の住むマンションへと向かった。
■第七話【部長】時の狭間で性行為
二十三時。駅からの道を足早に歩いて自宅マンションへ帰宅した。玄関に入ると力が抜け、スーツのまま着替えもせずリビングのソファで項垂れている。
さっきキャバクラで社長が話していた都市伝説の病。すぐに私自身の身に起きている事象のことだと気がついた。キャバ嬢の話を聞きながら、私にだけ起きている現象ではなかったのだと知り、最初はむしろホッとした。
しかし、その後に語られた後遺症の話があまりにショックだったのだ。
若返りの一年が終わってしまい性欲だけが残ったら、五十代の姿をした私が喫煙所で青木の長い指や柔らかい唇を見て欲情するという痴態を、晒すかもしれない。
五十四才のくせに青木に抱いてほしくて、真剣に迫ってしまう日がくるかもしれない。
みっともないエロジジイにはなりたくない。青木に蔑んだ目で拒絶されたくない。処理できない性欲を抱えた日々は想像しただけで辛く、堪えられなかった。あんまりな代償だ。
いっそのこと会社を辞め、青木と距離を置くために実家に帰ろうか。
そんなことも考え始めていた。
二十三時四十五分。
スマートフォンが振動し、画面を見ると青木からの電話だった。慌てて通話ボタンを押すと「リョウくんに会わせてください」と言う。
その一言で、青木も社長の都市伝説話を聞いて、私とリョウの関係に気がついてしまったのだと分かった。そうでなかったら常識ある男が、こんな夜分に突然訪ねてくるなんて言うはずがないから。
青木は怒っているだろうか、まさかリョウの正体が直属の上司だったなんて。今までの行為を気持ち悪く思い、嫌悪しているかもしれない。
さっきの電話は最寄駅からだから、十分もしないで、インターホンが鳴るだろう。
この期に及んで、青木に少しでも良く思われたく、室内に干してあった洗濯物をクローゼットに押し込み、部屋の隅に積んであった新聞紙を縛って納戸にしまった。
手を動かしながらも、若返りに期限があったことで押し寄せる後悔は尽きない。
秋までは毎週だったリョウと青木の逢瀬を、意図的に隔週へと減らしていたのは、リョウの若さに嫉妬していたからだ。
おかしな話だ。自分が自分に嫉妬しているのだから。しかし青木がリョウの見た目を褒めると、五十代の自分が惨めに感じてしまうのだから仕方がない。
どうか五十四才である私にも目を向けてほしいという願望から、リョウの登板を少なくし部長として食事に誘いポイントを稼ごうとした作戦は、当然ながら実を結ばなかった。
こんなことなら、もっと頻繁に若い身体で青木に会いに行き、抱いて貰えばよかったのだ。
深く溜息をついた時、インターホンが鳴った。
零時五分前。
リビングに青木を招き入れる。
「すいません。こんな時間に。どうしても確認し……」
何か言いだそうとする青木の声を上司という立場を利用して遮り、話を始める。
「青木。色々と疑問があるのかも知れないけれど、今夜は勘弁してくれるかい?すまないね、気分が優れなくて」
「あっ、そうでした。大丈夫ですか?」
「いや、少し眠れば治ると思うんだ。リョウは二時間もしたら帰ってくるはずだ。リビングで待っていてやってくれるか?それからリョウにも今夜は難しい話をしないでやってほしい。どうやらあの子はもうすぐ居なくなってしまうから、良くしてやってくれないか……」
頼む、と頭を下げた。
青木は「はい」も「いいえ」も言わずに私を見ている。都合が良すぎる提案に呆れているのかもしれない。あるいは正体がバレたリョウのことなど、抱けるわけがないと思っているのか。
それでも少し間を置いて「待たせてもらいます」と言ってくれた。
「ありがとう。シャワーを浴びて先に寝かせてもらうよ」
あくまで私は、都市伝説など無いものとして振る舞った。
零時半。
シャワーを浴び部屋着に着替え、リビングへ顔を出す。青木はスマホを弄りながらソファに深く座り込んでいた。
「青木もよかったら、シャワーを使うといい」
タオルと簡単な着替えを渡し、私は寝室へと引き上げた。
彼がシャワーを使う音が聴こえてくると、今夜、リョウを抱いてくれるのかもしれないと、少し期待が高まった。
いずれにしろ、ほぼ正体がバレた今、青木とセックスできるのは今夜が最後のチャンスだろう。
午前二時にアラームが鳴るようスマートフォンをセットし、少しでも寝ておこうと私は眼を閉じた。
そう簡単には入眠できずに寝返りを繰り返していたが、いつの間にか夢の中にいた。子どもの頃に飼っていた犬の夢だ。父がどこかから貰ってきたミックス犬で、とても大きく毛足が長かった。
外で飼っている犬だったけれど、あまりに寒い日には私の部屋に入れ、一緒に眠った。部屋の隅にいたはずの犬は、いつの間にか私の布団に入ってきてくれるから、抱きしめて撫でながら眠るのが大好きだった。
犬の温かさを感じ、モフモフとした毛を指で弄び、ピチャピチャとした水音を聴く。
……。え?
夢の中から急速に意識が浮上すると、私の布団の中に何かが潜んでいるのに気がつき、身体が強張る。
そっと掛け布団を捲ると、信じられないことに私が貸した部屋着を身につけた青木が私の陰茎を咥えていて、目が合った。
慌てて目をそらし、壁の時計を見れば一時五十分。
「ど、どうして?」
ようやく声が出る。青木は私の問いなど無視し、温かい口で丁寧に口淫をしてくれる。
「青木?」
彼が必死に舐めてくれても、五十四才の陰茎はまったく勃ち上がらない。それでも青木はその行為を続けてくれた。
二時。突然、枕元でアラームが鳴る。それと同時に一瞬の浮遊感があり、私はリョウになった。
陰茎もグンと大きさを増し、硬く勃ち上がる。
「リョウ……」
青木に全てを目撃されて、もう何の言い訳もできない。
「すまない」
そう謝ってしまったけれど、その言葉を塞ぐように唇を合わせてくれた。青木は可笑しな都市伝説の病に罹った私が、気持ち悪くないのだろうか?
リョウとして昂ってしまった私の性欲は、もう止まれない。彼の首に手を回し口内に入り込んでくる青木の舌に、夢中で吸い付いた。
青木は「ローションはありますか?」と、丁寧な言葉でリョウに問いかけてくる。引き出しを指差せば、そこからいつも私が自慰に使っているボトルを取り出す。
ローションを纏ったヌルヌルの指が後孔に入り込んでくれば、私はより興奮する。
はぁはぁと呼吸を荒くし、指の動きを誘うように腰を揺らめかせ、青木に先を急がせる。
「ヒ、ヒビキさん」
もうその名で呼ぶ必要はないのに、そう呼べば青木は目を細めて笑い「リョウ……」と声にしてくれた。
指を増やされ、いい処を擦られるから、陰茎から先走りが蜜のように溢れ出る。
「脱いで」
中途半端に膝まで下げられていたスウェットとトレーナーを、脱ぎ捨てる。ヒビキも裸になり、彼の勃起したものが顕になった。
さっきまでおじさんだった私を相手に、勃ってくれたことに安心した。
だから大胆にも彼の腰に跨る。ヒビキの硬さを手のひらで確かめ、自分の後孔に彼の陰茎を充てがう。
ヒビキは余裕の表情で「入れて、リョウ」と私の胸の突起を撫でるから、腰を落としズブズブと埋めていく。
「あっ、んぁっ、んっ、あっ」
徐々に腹の中がヒビキでいっぱいになっていき、苦しくて、でも満たされて、もう自分では身動きが取れない。
「ほら、リョウ。動いて」
そう言われても首を振るしかできない。
「できるだろ?リョウ」
「む、むり、う、動いたらイッちゃう、から、むり」
ヒビキは、ふふっと笑って下から突き上げるように腰を動かし始める。
「やっ、あっ、だめ、あっ」
こんな痴態を晒すのも、二十才のリョウだから許されるのだと思いながら、喉から漏れる高い声を抑えることはできない。
奥に当たる快感に震え呆気なく白濁を飛ばすと、ヒビキも艶っぽい小さな呻きとともに吐精したのが分かった。
「も、もう一回、ねぇ、もう一回、ヒビキさんっ」
「あぁ……朝まで、何度でも、何度でも、しよう、リョウ。かわいいリョウ……」
私は何度も何度も求め続け、ヒビキはそれに応えてくれた。
「ねぇ、また証をつけて」
そう強請って首元を晒し、チリっとした痛みと共にキスマークもつけてもらった。
「エロっ」
自分でつけたくせに、その箇所を指でなぞったヒビキが呟く。そして私の足を自分の肩に乗せ、また硬くなった陰茎で後孔を貫いてくる。
時間を気にせず、シーツが乱れるのも構わず、ヒビキにしがみついて「いい、すごく、いいっ」と嬌声をあげ続けた。
何度目か分からないけれど、またイきそうだ。
中がギュッと収縮してヒビキの精を搾り取るように締め付けている。手の先や足の先までがピリピリと痺れ「あっ、んあっ」と喘ぎが止まらない。ヒビキも随分と良さそうに、息を乱し腰を振っている。
再び突然の浮遊感が私を襲った。そして気持ちがすっと冷める。暴発寸前だった陰茎も瞬時に萎えた。四時になってしまったのだ。
異変を感じ動きを止めたヒビキ、いや青木と目が合う。目の前にいた綺麗な顔をしていたリョウから、年をとった部長の顔に変わって、彼も萎えてしまったかと思った。
しかし更に興奮したかのように「部長、部長、山野部長っ」と更に激しく強く突き上げきて、彼は私の中で果てた。
そして、五十四才の顔にチュッと遠慮がちにキスをくれた。
呼吸を整え、脱ぎ散らかした服を身につける。青木はまだベッドの上で裸で横たわっている。
引き出しの上に置いてあった眼鏡と煙草を手に取り、私は一人、ベランダに出た。
外はまだ真冬の寒さで、部屋に冷気が入らぬよう慌ててガラス戸を閉める。煙草に火をつけた時、青木が吐精した白濁が後孔からダラリと溢れ出て下着を汚したのが分かった。冷たい空気の中、その液体の熱さにブルッと身震いする。
一本吸い終わった頃に、ガラス戸が開き青木もベランダに出てきた。
「一本ください」
煙草を差し出し、火をつけてやる。
「驚いたかい?そりゃ驚いただろうね」
青木は何の返事もよこさない。
「さっきのキスマークも消えてしまうんだよ。ほら」
首元を見せるが、そもそもまだ夜明け前で外は暗く、青木から見えたかどうかは、分からない。
裸足の足からしんしんと冷えて、自然と肩を寄せ合った。
やはり青木は同情してくれているのだろう。私を可哀想だと思っているのだろう。彼はやさしい男だから。
「一つだけ教えてください。一年経つのはいつですか?」
「あぁ。初めて気がついたのは、桜が満開になった日だったんだよ、会社の側の焼き鳥屋に皆で花見がてら行った日。青木もいたね。覚えているかい?」
「はい」
「それより前から始まっていたのかもしれない。だから終わりが来るのは明日だっておかしくない。どんなに長くても残り一ヶ月、桜が満開になる頃だろう」
「クシュン」
青木がくしゃみをするから「寒いね」と二人で部屋に戻った。
五時。
常夜灯のみの暗いリビングで、青木は着て来たスーツに着替えている。
そろそろ電車が動き出すから、と自宅マンションへと帰っていった。見送る時も玄関の照明を付けず、暗いまま見送った。
私の姿を直視して欲しくなかったし、青木だってこんなおじさんとセックスした現実と向き合いたくないだろう。
それでも、玄関ドアが閉まるとき「部長、おやすみなさい」と触れるだけのキスをしてくれた。
私は再びベランダに出て下を覗き、エントランスから青木が姿を現すのを見ていた。
外へ出た青木はわざわざ上を見上げ、ベランダにいる私に気がつくと手を振ってくれた。
見えなくなるまで見送り、シャワーを浴びて下着を替えた。
その日、私は会社を休んだ。どんな顔をして青木に会えばいいのか分からなかったし、酷く混乱していたから。
勤続三十年で、初めてのずる休みだった。
一日中だらだらとベッドの上で過ごし、一歩も家から出なかった。
それでも夜中二時にはアラームを鳴らし、まだリョウの身体になる現象が失われていないか、わざわざ確かめた。
洗面所の鏡の前まで行き身体中を検分し、ちゃんと若返っていることを知れば安心できた。
首を見ると、昨日つけてもらった赤く鬱血したキスマークが、リョウの身体には残っていた。
ベッドに戻り、青木との行為を思い出して自慰をすれば、じきに眠みが訪れる。
ウトウトしながら、昨日の出来事を一生の思い出として生きていこうと決めた。
若返りが終わったら、五十代の身体が持て余す性欲をコントロールする為に、毎晩毎晩自慰をして制御する努力をしていきたい。坐禅や写経に通って精神統一をするのもいいかもしれない。
翌日から、社内ではできるだけ何でも無いように振る舞った。青木とは意図的に距離を置き、煙草も我慢して喫煙所にも行かなかった。
もちろん金曜には、私からもリョウからも青木を誘わなくなった。
しかし、青木が「部長、夕飯を食べに行きましょう」と言う。更に食事が終われば「家に行ってもいいですか?」とついてくる。
青木はリョウとの残り少ない時間を惜しんでくれているのだろうか?
順番にシャワーを浴び、青木がリビングのソファで眠れるよう毛布を用意してやり、私は「おやすみ」と寝室へ籠る。
すると青木は必ず二時少し前に私の寝室に来て、行為に及ぼうとする。
シワが深い私の頬にキスをして、勃たない私のものを咥えて舐める。二時に私が若返れば、以前のように「リョウ、リョウ」と名を呼んで抱いてくれる。
何回かそんな金曜を過ごすうちに、青木は翌朝まで泊まって行くようになった。
近所の早朝からやっているベーカリーまで、青木がパンを買いに行ってくれる。そのパンを食べ、コーヒーを飲み、二人で朝のニュース番組を見ていた。
どうしてこんな状況になっているのか、不思議に思いながら。
テレビの中でキャスターが「今年は例年に比べ桜の開花が早いでしょう」と言っていた。
いよいよ、終わってしまうのだ。青木と過ごす幸せな金曜も……。
青木はニュース画面を見ながら「部長の若返る病、早く終わるといいですね」と言ってきた。
なぜ?どうして?私は疑問でいっぱいだった。
■第八話【部下】念願叶って部長と……
昨年より十日も早く桜が開花した。
山野部長は桜が満開になる頃に若返り現象が終わると考えているようで、桜の話題が耳に入る度に眉毛がハの字の、酷く悲しそうな顔をする。
やはり、リョウの姿になるのが好きだったのだろうか。確かにリョウは美しい。シワもシミもない若い肌だけでなく、少し幼さを残す甘めの顔立ちは綺麗に整っていて可愛い。
若い頃の部長はどれだけモテたのだろうと、今更心配になってしまう程だ。
部長が都市伝説と囁かれるような病に罹っていることが分かってから、俺はリョウを「若い頃の部長」とハッキリ認識し抱いている。
好きになった人の、若い頃の容姿と接触が持てるなんて、そりゃ興奮するに決まっている。
確かに都市伝説のことを知った日には、俺も随分と混乱した。
まず確かめたかったのは、リョウの姿の時、心の中は誰なのか?ということだ。
部長からリョウになり、また部長に戻る時間をベッドで共にして分かったことは、身体のみが若返るということだ。
心は地続きで、リョウの間も中身は部長。もちろん部長に戻ってからもリョウになっていた時の気持ちが持続している。
ただ、リョウになっている間は少しだけ脳も若返るのか、行動が大胆になる。それは俺にとってプラスポイントでしかない。
リョウとしてヒビキを好いてくれているなら、山野部長としても部下である俺を嫌いなわけがない。今ではそう信じて、疑っていない。
おそらく残り数日で、部長の若返り現象は終わる。そしたら、後遺症として強い性欲が残るのだという。
つまりだ。
どうやら今は勃たない部長と、セックスをすることができるのだ。俺はその日がくるのが楽しみで仕方がない。
きっともうすぐその日はやってくる。
金曜に部長のマンションに泊まり、土曜の朝を迎えるのも三回目となった。
リョウの姿で高い声で喘いでいた部長が五十代に戻り、眠りに着いたのは四時過ぎだ。二人とも裸のまま互いの体温を感じ、気持ちよく眠っていた。
枕元でスマホが鳴り、意識が浮上する。眼を開ければカーテン越しに明るい陽射しが燦々と降り注いでいた。「土曜に誰だろう?」と画面を見ると、社長の息子からで慌てて通話ボタンを押す。
「青木。一昨日、本社に送ってくれって頼んだ試作品、クライアントの東京事業所に送っただろ?」
「え?はい。東京事業所へという、指示でしたから」
「あーん?俺は本社って頼んだはずだぞ。先方はカンカンだ。すぐにピックアップしてこっちへ運んでこい、夕方までにだ」
「名古屋に?」
「そうだ」
部長にも全て聴こえていたようで、眠そうにしながらもベッドの上で身体を起こし、俺の顔を眺めている。
時計を見るともう昼の十二時近かった。
色々と言いたいことはあったけれど、今日の夕方にあの試作品がないと困るのは確かなのだろう。
「クライアントの事業所に寄って、本社へ行ってきます」
部長にそう伝えながら、昨日着てきたスーツを身につける。
「青木は事業所に電話をしてくれ。私が取りに行くから。その間に一旦家に帰り着替えなさい。東京駅で落ち合おう。私も一緒に本社へ行くから」
申し訳ないと思ったけれど、部長が一緒に行ってくれたほうが心強い。
「よろしくお願いします」と頭を下げた。
新幹線の中からスマホでクラウドにアクセスし、社長の息子とのメールやり取りを確認したが、確かに事業所へという指示を受け取っていた。
理不尽に思いながら車窓を見れば、満開には遠くても、ピンクに色付いた桜の木が何本も目に入った。
名古屋駅に着いたのは十五時半だった。途中でメッセージが届き、本社ではなく息子も暮らす社長宅へ持って行くことになった。
十六時に到着するなり「遅いっ」と怒鳴ってきた息子は俺が一人ではなく、部長と一緒だったことに驚いている。
「部下が指示通りに行ったことを一方的に責められるのは、黙って見ていられませんから。貴方は自分が指示を間違えたと非を認め、運んできくださいと頭を下げることができないのですか?」
息子はムスっとして「とにかく急ぐからそれを寄越せ」と荷物を奪い、車で出掛けて行った。
息子が身勝手なのはいつものことだが、部長が自分の味方をしてくれたことで、溜飲が下がった。
「あれ?良ちゃん。どうした?」
「あぁ、健ちゃん。健ちゃんの息子に振り回されたんだよ。もう少し何とかならないのか?あの子は。小さい頃は素直だったのに」
「また迷惑かけたのか、あの馬鹿。それは申し訳なかった。やっぱり一度、違う会社に出さないとダメだな」
普段の社長と部長の会話からは掛け離れた親しさに、驚く。
「青木も土曜なのにご苦労だったな。良ちゃんちで、美味い物でも食べてから帰れよ」
「良ちゃんち?」
「すぐそこの居酒屋だよ。青木は知らなかったか?俺たち小学校から大学まで同じ学校に通った幼馴染なんだ」
「え?いや、全く知りませんでした」
社長夫人がコーヒーを運んできてくれたから、ソファに腰を落ち着け、ご馳走になる。
「良ちゃんは男前で格好良いのに、可愛いところもあってな。二十才の頃なんてモテてモテて、仕方がなかったんだぞ。な?」
「うるさいよ」
「写真とかないんですか?」
「青木も何を言うの?」
「写真、あるよ、ある。見るか?今持ってきてやる」
思わぬところでリョウの写真を見る機会に恵まれた。
社長は何冊ものアルバムを見せてくれた。そこに写っていたのは、正に自分のよく知っているリョウで、とても不思議な気分だった。
「この写真は?」
「それは子どもの頃の誕生日パーティだ。確か三月だったな、良ちゃんの誕生日」
「うん?あっそうだ。……今日だ、五十五才の誕生日。すっかり忘れていたよ」
「五十過ぎたら年齢なんてあやふやだもんな」
そう笑いながらも、飲み会好きの社長は「思い出したからには、祝ってやらねぇと」と、色んな人に電話をかけ始め、人を集めている。
会場は、部長のお兄さんが継いでいるという実家の居酒屋らしい。
暇を持て余したおじさんたちが、あっという間に十人以上、店に集まってきた。
皆、男子高の同級生だという。
「おぉ、良ちゃん、誕生日だって?おめでとう」
あちらこちらで、皆が乾杯をしている。
社長が俺のことを「良ちゃんが可愛がっている部下の青木だ」と説明してくれるから、悪い気はしなかった。それに、おじさん好きの俺にとっては心躍るものがあった。
しかし皆が皆、俺に言うのだ。
「良ちゃんは、格好よかった」「良ちゃんは、可愛かった」「良ちゃんは、俺たちのアイドルだった」と。
「知らなかっただろ?若造」とでも言うように、昔の部長を俺に自慢しようとする。更に、自分の手柄のように部長が上級生の男子にも、他校の女子にもモテまくったエピソードを聞かせてくる。何なのだろうか?
俺だってリョウを知っている、アンタ達に負けないくらい。そう言いたかったが、言えるわけはなかった。
当の部長は誕生日を祝ってもらう立場のはずが、ビールや料理を運んだり、皿を下げたりといつの間にか店の手伝いをしていた。俺は、烏龍茶を飲みながらおじさん達の語る「良ちゃんの昔話」をひたすら聞かされ続けた。
「はい」「はい」と相槌を打ちながら、頭の中で「そうだ!リョウと写真を撮りたい!」と思いつく。一度、部長との添い寝写真を無理やり撮ったことはあったけれど、もうすぐ消えてしまうリョウとの画像は一枚もないから。
よく飲んでよく食べたおじさん達は、社長に連れられて次の店へと移動していった。
部長は「後で行くから」と店に残り、手を振って皆を見送っている。おじさんたちは、既に何を理由に飲み始めたのか忘れているだろう。
「青木、帰ろうか」
店のエプロンをお兄さんに返した部長は、俺にそう言った。
「今なら最終の新幹線に間に合うだろう」
「はい」
部長が、あのおじさんたちではなく自分を選んでくれたような気がして、とてもうれしく思った。きっとまた、懐いた犬のように見えない尻尾をブンブンと振ってしまっているだろう。
新幹線は零時前に東京駅に到着した。そのまま電車を乗り換え、マンションの最寄り駅に向かっている。
「あの、部長。実はリョウと写真が撮りたいんです。一枚くらい残しておきたくて。今夜またマンションにお邪魔してもいいですか?」
「写真か……。そうか、そうだね。撮ろうか、一緒に。来週の金曜まで待っていたらリョウは居なくなってしまうかもしれないからね、今夜撮るのがいいね」
部長はまた酷く悲しそうな顔になった。
深夜一時前には、部長のマンションに辿り着いた。交代でシャワーを浴び、昨晩も借りた部屋着に着替えた。二人でベッドに入り、天井を見上げながら大人しく二時になるのを待つ。
「そうだ、部長。日付が変わってしまいましたが、お誕生日おめでとうございます」
「フフ。ありがとう。青木に祝ってもらえて、うれしかったよ」
「社長と幼馴染だとは、驚きました」
「私、結構有名なとこに就職したんだけど、社会人二年目で上役と不倫してね。相手はもちろん男性だよ。結局バレて、勤め先を首になって。困っていたところを健ちゃんに拾ってもらったんだよ」
「なるほど」
「それにしても、今日は移動距離も多くて疲れたな」
「はい、本当に……」
俺が欠伸をすれば、部長も大きな欠伸をした。二時まではまだ五分あった。部長の方に身体を向け、肩に顔を埋め甘えた。部長も俺のほうを向いて、背中に腕を回してくれた。
……。
ハッとして壁の時計を見ると、もう三時半だった。いつの間にか二人とも寝入ってしまったようだ。互いに何度か寝返りを繰り返したようで、リョウはこちらに背中を向けていた。
「リョウ、俺、寝っちゃってたよ。リョウ?」
背中を揺すって起こそうとすると、また寝返りを打って身体がこちらを向いた。
「リョウ?」
熟睡している顔を覗き込み、その後、スマホを手繰り寄せ時間を見る。間違いなく深夜三時半だった。けれど、隣に眠っているのはリョウではなく、山野部長そのものだ。
どうやら治ってしまったようだ、若返る病が。もうリョウとは写真も撮れないし、二度と会えないのだ。
けれど、後遺症の話が本当であれば、性欲は部長に残ってる。ようやく部長とセックスすることが叶うだろう。
掛布団の中に潜り込んで、眠っている部長のスウェットをゆっくりズラし、太腿を撫でた。
ピチピチと張りのあるリョウの肌に比べ、部長の皮膚は柔らかく触り心地がいい。
気持ちが急いてしまうけれど、まずは部長の陰茎が勃ち上がるのか確かめなければ先へは進めない。慎重に不快感を与えないように、ゆっくりと先端を舌で舐め、徐々に頬張るように咥えこんでゆく。
部長が「んっ」と鼻にかかった息を漏らしたあたりから、陰茎は質量を増し、口の中で存在感を顕にしていった。
トレーナーの中へと手を伸ばし、胸の突起も指で弄る。乳首は少しカサカサしているけれど、感度は良くぷくりと膨らみ、擦るように触れば部長の呼吸が乱れてきた。
「ヒ、ヒビキさん?」
眠りから目覚めたての部長が問いかけてくる。俺は口淫を解き「違う、青木ですよ。部長」と返事をした。
「青木……」
「そう。部長、俺とセックスしましょうよ」
引き出しから勝手にローションを取り出し、たっぷりと指に纏う。リョウの身体とは違い、部長の後孔はしばらくの間、使われていなかったのだろう。硬く閉じたそこに指を捩じ込むと、部長はそれだけで興奮したように悶えた。
一旦指を抜き、更にローションを足した。今度はもう少し奥まで指で探っていくと、部長は俺にしがみついてくる。
渋くて頼りになってやさしい部長が、リョウよりも少しだけ低い声で「あっ、んぁっ、んっ」と喘ぎ、湧き上がる快楽に戸惑いを見せている。
指を増やし、リョウが好きだった箇所に触れれば、いい場所は同じらしく「ダ、ダメっ」と部長の声が裏返った。
中で動かしている指に、部長の粘膜が纏わりついてきて、実にイヤらしい。
「ねぇ、部長。分かってます?これリョウの身体じゃないですよ」
「へ?」
「ほら」と、反対の手で硬く勃ち上がった陰茎を上下にしごいてやれば先端から蜜が溢れこぼれ落ちた。
部長は引き出しの上の眼鏡を手探りで取り、顔に乗せ自分の股間を覗き込む。
「し、白髪が、ある」
そんなことで若返っているかどうか確かめようとする部長が、可笑しくて笑ってしまった。
指をもう一度引き抜くと「ふぁっ」と気持ちよさそうな声を上げる。
「もう少しよく解しますから」
そう告げ、更にローションを足して再度指を突っ込み、クチュクチュと卑猥な音を立てながら入り口を広げるように弄った。
部長は混乱しているようだった。
リョウではない自分が、部下である青木とセックスしようとしている現状に。それでも部長の身体はあからさまに快楽を求めて、腰を揺らし、より強い刺激を求めようとしている。
「ぶ、部長、もう、もう、挿れさせてくださいっ」
コクリと頷いてくれる部長のスウェットと下着とトレーナーを剥ぎ取り、自分の着ていた物もベッド下に投げ捨てた。
部長の足を持ち上げ、反り返ったモノを宛てがい、自重をかけてズブリと押し込む。
腹の中がいっぱいで苦しそうにする部長の表情に、俺の興奮は加速する。身体を折りたたみ密着して唇を合わせた。
舌を絡め取り、口内を舐め、唇を喰む。接触している素肌は、リョウより少しだけ腹回りの肉付きがよく、そのクッションが堪らなく心地よい。
熟成した男の身体と色気は、俺にとって媚薬でしかなかった。
「う、動いて、青木っ」
部長の中に挿れた陰茎をゆっくりと引き出し、ズシンと奥へ押し込む。またゆっくりと引き出し、奥へ強く捩じ込む。
引いても押しても、部長は嬌声をあげ気持ちよさそうに、首を反らす。それを何度も何度も繰り返した。
「もう、もう、イきたい、あ、青木、イきたい、イかせて、ねぇ、あっ、もう、あっ、イかせてっ」
苦しい程の気持ち良さが、部長を襲っているのだろう。
「ねぇ、もう、もうダメっ、あっ奥っ、イ、いい、ねぇ、あっ、イ、イっちゃっ」
震えながらイった部長の顔を、逃さずしかと見た。恐ろしく艶っぽく、最高にエロかった。
「部長、もう少し、だけ、付き合って、くだ、さいっ」
達して敏感になっている部長の中に、ガクガクと腰を打ちつければ、更なる甘い声をあげ続けた。部長の後孔はビクビクと収縮し搾り取るように俺を締め上げる。
あまりの気持ち良さに頭が真っ白になり、呻きながら吐精した。
二人で、はぁはぁと息を乱し、何度も何度も触れるだけのキスを交わした。
呼吸が落ち着いても何の会話もなく、裸のまま後ろからただただ部長を抱きしめ、余韻に浸った。
外はだんだんと明るくなってきて、もうすぐ夜が明ける。
俺はベッドを降り、脱ぎ捨てた服を身に纏ってカーテンを開けベランダへ出た。空は紅く朝焼けをしていて、遠くにはスカイツリーも見えた。あぁこの景色だったのだ、リョウがアイコンにしていた写真は……。
部長も服を着て窓際までやってくる。俺の背後に立ち同じ空を見ながら「綺麗だな」と言った。そして「今までありがとう」とまるで別れとも取れる言葉を口にするから、ゆっくりと振り向き、眼鏡を掛けたその表情を見る。
それは桜の満開が近づくと共に見せていた、あのハの字眉毛の酷く悲しそうな顔だった。
俺はようやく部長の悲しみの理由に思い至る。部長は俺が若返ったリョウのことだけを好きだと、思い込んでいるのだ。違うのに。俺が好きなのは部長なのに。
「部長……」
うんと愛を込めてそう呼びかけると、数センチ低いベランダへと降りてきてくれた。
そっと顔を寄せ唇を合わせる。部長はそれだけで「ぁっ」と甘い吐息を溢した。
きっとすぐに気がつくだろう。俺がリョウよりも部長を愛していることに。
今後は、後遺症だと言われるその性欲の全てを、俺に委ねてくれればいい。
